岡 国・地域によって、医療や保険の仕組みは違いますから、米国のモデルをそのまま日本に導入できないことはわかっています。私は北欧やスペインでも医療事情を視察しましたが、IHNのような地域医療の統合ネットワークが形成されています。IHNといっても国・地域によって多様性があり、日本の現実を踏まえたうえで、理想を実現するために努力することが大事だと思います。
法人全体でデジタル推進の仕組みを整備
北原 敬和会ヘルスケア・スマートリンクを円滑に機能させるためにどんなことに取り組んでいますか。
岡 デジタル化が大きなカギだと思っています。これまでは紙ベースで情報をやり取りすることも多かったのですが、敬和会ヘルスケア・スマートリンクの全施設をつなぐ情報ネットワークを整備し、デジタルによる情報共有に取り組んでいます。
基幹業務システムや通信ネットワークを構築し、電子カルテなどの情報を共有できるようにすることで、患者中心の医療と業務の効率化を同時に進めようとしています。紙ベースで情報を動かしていた時に比べると、情報共有のスピードが格段にアップしました。たとえば、必要な書類を取りにいかなくても、基幹業務システムにアクセスするだけで情報が手に入るようになりました。
北原 職員の方々からは、どんな反応が返ってきていますか。
岡 まだ、施設によってICTの整備状況に差があるので、「うちの施設でも早く整備してほしい」といった声があります。私は年間を通して全施設の役職者と面談しており、一人ひとりの要望を聞いて、デジタル化を進めるうえでの参考にしています。
北原 日本全体でICT・デジタル人材が不足しているといわれる中、敬和会ではどのような組織体制でデジタル化を進めているのでしょうか。
岡 我々と一般企業の大きな違いの一つとして、職員の8~9割が国家資格取得者であることが挙げられます。それぞれの国家資格を取得するための教育課程で、デジタルに関して学ぶ機会はこれまで十分ではありませんでした。
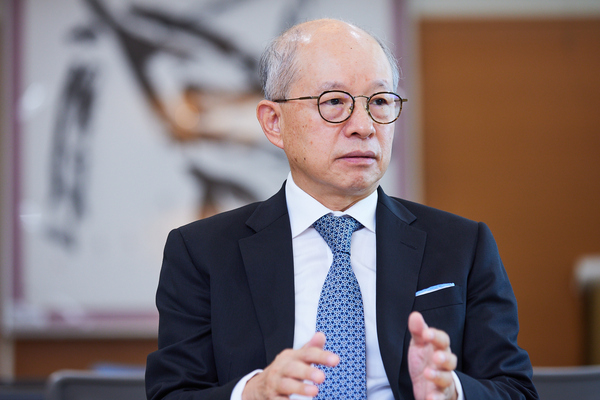
Keiji Oka
社会医療法人敬和会 理事長
学習指導要領の改訂で、小学校から高校まで情報教育のカリキュラムが強化されていますから、今後はかなり変わっていくと思いますが、そうなると現在の職員と将来入ってくる職員のデジタルリテラシーにギャップが生まれるので、それはそれで問題です。
そうしたギャップを生じさせない意味でも、敬和会では理事会の直下にデジタル推進委員会を設け、デジタル活用とデジタル人材育成に同時に取り組んでいます。
中村 具体的にはどのような活動に取り組んでいるのですか。
岡 デジタル推進委員会のメンバーは、それぞれが分野別の課題を与えられています。たとえば、臨床研究におけるデータサイエンスやAI(人工知能)の活用に取り組んでいるメンバーもいれば、デジタルによる職員教育を推進するデジタルアカデミーやITによる業務改善をテーマにしているメンバーもいます。
中村 メンバーの方々は、ふだんは病院や介護施設などの現場で働いていらっしゃるのですか。
岡 そうです。ICTに詳しいとか、デジタルに関心があるといった職員を中心に人選しています。
中村 現場の業務が忙しい中でデジタル推進の活動もこなすのは大変だと思いますが、どのような制度設計をされているのですか。
岡 1週間にどれくらいの時間をデジタル推進の活動に充てられるか、本人と現場管理者の話し合いの中で決めています。他の職員に代わってもらえる仕事があれば、デジタル推進の活動を増やすといった調整をしています。
そのうえで、デジタル推進の活動時間に応じて、手当を支給しています。時間外労働になってしまうと本人の負担が大きいので、デジタル推進活動もすべて労働時間内に収めています。
中村 個人の自己研鑽や自己犠牲に頼るのではなく、人事制度を含めて組織的にデジタル推進の仕組みを整備していらっしゃるのは素晴らしいと思います。
患者と一緒に治療やケアのあり方を考える
北原 敬和会が目指す患者中心の医療を実現していくためには、患者とのエンゲージメントが重要テーマの一つになると思います。これまで医療提供者主体で患者のケアや治療が行われてきましたが、これからは医療チームの意思決定プロセスに患者自身が積極的に関与できるようにすることで患者エンゲージメントを高め、治療のアウトカム(成果)を向上させることが必要ではないでしょうか。


