なぜ「共生」ではなく、「協生」なのか
日本総研の石川氏が問題提起で示したように、「自律協生社会」を実現するうえでは、東京や会社に縛りつけられているヒト、カネの流動化をいかに促すかということが重要なポイントだ。
その有効策を示唆する取り組みを紹介したのが、NTT東日本社長の澁谷氏である。

代表取締役社長
澁谷直樹氏
京都府出身。京都大学工学部卒業後、日本電信電話(NTT)入社。2002年CSIS(米国戦略国際問題研究所)客員研究員、2010年東日本電信電話福島支店長、2014年ネットワーク事業推進本部設備企画部長を務め、その後、同社代表取締役副社長・ビジネス開発本部長・デジタル革新本部長。2020年日本電信電話代表取締役副社長(CDO、CTO、CIO)を経て、2022年より現職。
NTT東日本は、パーパスとする「地域循環型社会の共創」の実現に向け、農業や交通、医療、文化芸術活動など、ICT(情報通信技術)カンパニーの枠を超えた多彩な事業を展開している。自治体や企業、団体、市民とのコラボレーションによる事業も多い。
「社員がみずから手を挙げ、地方の方々と一緒に事業を始めるケースもあります。東京の本社から北海道に移住し、アグリテック(農業テクノロジー)の共同事業に専念している社員が代表例です」と澁谷氏は説明した。
同社は、こうした共同事業の種を増やすため、社内外での副業を促進する制度を導入。さらに社員の“働き方改革”も踏まえ、リモートワークをスタンダードとし、日本国内であれば居住地を自由に選べるルールも採用した。時間や場所に囚われず働ける環境を整え、地方創生に貢献したい社員が、行動に移しやすいようにしている。
澁谷氏は、「テクノロジーとネットワークの進化によって、社員がどこにいても、東京にいるのと同じ環境で働けるようになっています。当社で培ったビジネス経験でそれぞれの地域に何らかの刺激をもたらしてくれると嬉しい。地方に行った社員たちには、『地元に染まるのではなく、かき混ぜてほしい』と言っています」と語った。
この澁谷氏の発言を受け、パネルディスカッションの途中で双方向コミュニケーションツールを使った参加者へのアンケート調査が行われた。
「副業・兼業をしたことがありますか」との問いに対し、「はい」と答えたのは40%。「副業の目的は」との問いについては、「自己実現」が39%、「社会貢献」が24%、「スキルアップ」が17%、「副収入」が14%という結果になった。
スマートフォンを使ってアンケートに答えると、その場で集計結果が表示される仕組みは、参加者にとって興味深い体験だったようだ。
パネルディスカッションの後半では、人材だけでなく、東京に集中するIT企業やスタートアップ企業をどうすれば地方に呼び込めるかについても議論された。
日本デザイン振興会理事長の深野氏は、国内の高等専門学校としては19年ぶりに新設された「神山まるごと高専(高等専門学校)」(徳島県神山町)の事例を紹介。
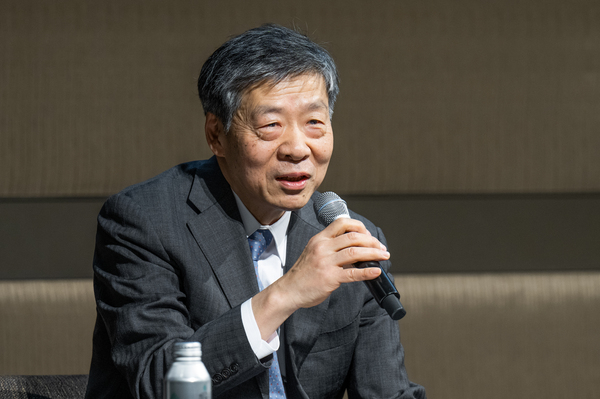
理事長
深野弘行氏
神奈川県出身。通商産業省に入省。米国スタンフォード大学客員研究員、秋田県出向(商工労働次長・部長)、経済産業省北海道経済産業局長、近畿経済産業局長、大臣官房商務流通審議官などを経て2012~2013年特許庁長官。伊藤忠商事に移り、2016年から同社関西担当。2019~2021年関西経済同友会代表幹事を務め、スタートアップエコシステムの支援などに取り組む。2021年より現職。
「中山間地域でありながら、神山町には数多くのIT企業、スタートアップ企業が進出しています。県内全域に光ファイバー網を整備するという徳島県の政策でインフラが整ったことに加え、町独自の取り組みとして国内外のアーティストに居住と活動の場を提供するなど、“新しいもの”を呼び込む取り組みを積極的に行ったからです。それがさらに発展し、進出したIT企業、スタートアップ企業などの支援を受けて新しい高専を立ち上げるプロセスがグッドデザイン金賞を受賞しました。この取り組みは町を発展させる巧みなデザインといえます」(深野氏)
白熱したディスカッションは2時間近くにも及び、最後には参加者からの質問に答えるQ&Aセッションが行われた。会場からの質問も双方向コミュニケーションツールによって、その場で問いかけられる仕組みだ。
最も多かったのは、「自律協生社会」について、「なぜ『共生』ではなく、『協生』なのか」という問いである。会場で参加していた日本総研創発戦略センター エクスパートの井上岳一氏は、「わかり合えなくてもいい。ただ『力を合わせて生きる』ことはできる。そう強調したかったからです」と意図を解説した。
まさに、自律したそれぞれの「個」が、互いの強みを活かしながら協力関係を構築し、価値やサービスを提供・享受し合うという「自律協生社会」の特性を言い表している。
最後に、日本総研取締役専務執行役員の木下輝彦氏が閉会あいさつで「“個”を活かし、協働・協生をベースにした新しい社会変革の重要性」をあらためて強調して締めくくった。その後、会場からパネリストへの惜しみない拍手が湧き起こり、シンポジウムは幕を閉じた。
【日本総研側の登壇者】
◎開会あいさつ

代表取締役社長 兼 最高執行役員
谷崎勝教氏
東京都出身。東京大学法学部卒業後、住友銀行(現三井住友銀行)入行。2013年三井住友銀行常務執行役員、2015年同取締役兼専務執行役員 兼 三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員。2019年同専務執行役員 兼 三井住友フィナンシャルグループ執行役専務グループCDIO、日本総合研究所代表取締役社長 兼 最高執行役員に就任。2023年より現職専任。
◎問題提起

調査部長
石川智久氏
福岡県出身。東京大学経済学部卒業。1997年住友銀行(現三井住友銀行)入行後、マクロ経済や金融制度に関する調査業務に従事。内閣府政策企画調査官(経済社会システム)、大阪府「万博のインパクトを活かした大阪の将来に向けたビジョン」有識者ワーキンググループメンバー、兵庫県資金管理委員会委員等を歴任。2023年より現職。著書に『大阪が日本を救う』、『大阪の逆襲』(共著)。
◎モデレーター

創発戦略センター エクスパート
三輪泰史氏
広島県出身。東京大学農学部国際開発農学専修卒業。東京大学大学院農学生命科学研究科農学国際専攻修士課程修了後、2004年日本総合研究所に入社。農産物ブランドや農業ロボットに関するベンチャー企業の立ち上げを主導。農林水産省の食料・農業・農村政策審議会委員、農村DX構想検討会座長、食料安全保障アドバイザリーボード委員や、農研機構アドバイザリーボード委員長、高知県IoP推進機構理事、官民ファンド社外取締役などの公的委員を歴任。
◎閉会あいさつ

取締役 専務執行役員
木下輝彦氏
愛媛県出身。神戸大学大学院研究科博士課程前期課程修了(商学修士)。三井住友銀行を経て、日本総合研究所へ。マーケティング分野を専門とし、アカデミアの世界を経て、日本総合研究所に復帰。主にヘルスケア業界の戦略に関するコンサルティングに従事。現在はシンクタンク・コンサルティング部門を担当。グロービス経営大学院客員教授、小樽商科大学非常勤講師。
株式会社日本総合研究所
〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目18番1号 大崎フォレストビルディング
Eメール:rcdweb@ml.jri.co.jp
URL:https://www.jri.co.jp/