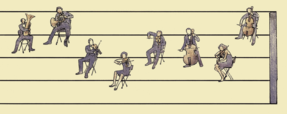-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
戦略プランニングを過剰に信奉していないか
1960年代半ば、戦略プランニングというアプローチが脚光を浴びるようになり、リーダーたちはこれこそ、事業部門の競争力を高める戦略を立案し、これを実行に移すための唯一最善策だと信奉するようになった。
フレデリック・テイラーが先鞭をつけた科学的なマネジメントに従い、この唯一最善策を思考することと実行することとを分離し、その専門家、すなわち戦略プランナーをスタッフとする新しい部署を創設した。この戦略プランニング・システムは、最良の戦略を生み出せるだけでなく、その戦略を実行する事業部門のマネジャーが間違えることなく追従できるように、戦略実行のステップをきちんと定めることをその旨とした。しかし、いまやだれもが気づいているように、必ずしも事はそう運ばない。
戦略プランニングはいまなお健在であるが、もはやその土台は崩壊している。にもかかわらず、いまだその理由を知る人は少ない。つまり、戦略プランニングと戦略思考が異なることが理解されていないのだ。
それどころか、戦略プランニングが戦略思考を台無しにし、その結果、マネジャーたちはビジョンと数字合わせを混同している。このような混同こそ問題の核心でもある。組織を成功に導く戦略は、やはりビジョンであって、けっして計画ではないのだ。
これまで実施されてきた戦略プランニングは、実は「戦略プログラミング」と呼ぶべきものである。すなわち、既存の戦略やビジョンを具体的な言葉で表現し、その詳細について詰めることなのだ。
戦略プランニングと戦略思考の違いを理解できれば、戦略策定プロセスのあるべき姿という原点に立ち返ることができよう。それは、マネジャーがあらゆる情報源(マネジャー自身の個人的な経験、組織内の他の人の経験から得た洞察といったソフトな情報と、市場調査などから得られるハードな情報)から学んだことを検索し、そこで学び取ったものをビジネスの方向性に沿ったかたちでビジョンへと統合させることなのである。
戦略プランニングの魔法から覚めたからといって、プランナーを不要と切り捨てたり、プログラミングする必要はないといった結論を拙速に出したりすべきではない。それよりも、企業は従来のプランニングの仕事を変えるべきなのである。プランナーは戦略策定プロセスの中心よりも、その周囲において貢献を果たすべきである。