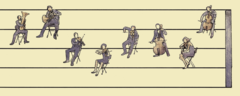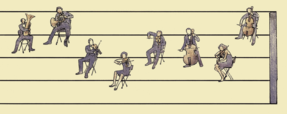-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
企業経営に蔓延する自己満足という悪癖
マネジメントの世界は、不可思議なことこの上ない。経営者は多額の報酬を与えられ、大きな権勢を振るっているにもかかわらず、およそ常識を知らない。少なくとも、流行のマネジメント理論、そしてマネジメント慣行の大多数はまったくの常識外れである。どうやら、マネジメントは不在というべきだろう。
なぜなら、経営者とマネジメントすべき対象との間には深い溝があり、それがさまざまな問題を引き起こしているからだ。その原因は、マネジメントが組織や顧客に奉仕するのではなく、「マネジメントのためのマネジメント」として行われることにある。
私は長い間、このような危惧を漠然と抱いていたのだが、ある時、明確に意識するようになった。それは、世界経済フォーラム(ダボス会議)1995年次総会でのスピーチを依頼され、テーマを相談するために、マネージング・ディレクターのマリア L. カタウィをジュネーブ近郊のオフィスに訪ねたことに端を発する。当初こちらは、「政府」というテーマを提案して、深く議論できるように1時間近くのスピーチ時間を求めた。
すると、彼女はこう答えた。「企業経営について話していただけませんか。それに、CEOの多くは、スピーチが始まって15分以上過ぎると、集中力を失っていきます」
私は、ミーティングから戻った後にもう一度考えて、先方の要望に従うことにした。またとない機会だと思ったからだ。スピーチの表題を「マネジメントに関する10の考察」として項目を列挙し、カタウィにファックスで送ったところ、幸いなことに彼女はこれを受け入れてくれた。いやそれどころか、このテーマに大いに関心を示してくれた。
このようにして私は、ダボス会議で10分間を与えられ(スピーチ時間は最終的に10分にまで削られた)、10項目について話すことになった。各項目1分ずつである。
『ハーバード・ビジネス・レビュー』の場合はさらに寛容で、その10項目に肉づけする機会を与えてくれた。ただし、読者の皆さんは心していただきたい。この論文の内容は、何らかのかたちで、およそあらゆる人々を不快にするに違いないからだ。