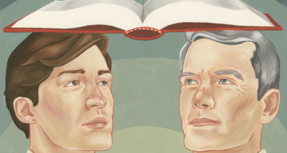-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
「アイデアの経済」における人財マネジメント
素晴らしいアイデアを見つけるのはとても難しい。スイスの巨大製薬会社ロシュの会長兼CEO、フランツ・フーマーはそのことをよく承知している。いわく「我々の研究活動は規模の経済とは無縁です。ロシュは現在、全世界で毎年40億ドルをR&Dに投じていますが、研究活動の世界に存在するのは規模の経済ではありません。アイデアの経済なのです」。
フーマーによれば、コスト効率ではなく、アイデアと知的ノウハウによって経済性を働かせる能力を競争優位の源泉とする企業がますます増えているという。このことを現実のマネジメントに置き換えれば、リーダーはAクラス社員が活躍できる環境を創出しなければならないということである。
この一握りのAクラス社員は、与えられた経営資源以上の価値を創出するようなアイデアや知識、スキルの持ち主たちである。たとえば、新しいアルゴリズムを考案したプログラマーや、新薬の構造式を考え出した医薬品研究者を想像してみてほしい。彼ら彼女らによるイノベーション一つで、10年間、会社全体が左うちわで過ごせることだってある。
才気煥発で創造性に優れた人材を確保することが重要であることに、ほとんど異論はなかろう。ただしビジネス競争にあっては、そのような人材を集めただけではまだ道なかばである。
世界有数の広告会社WPPのCEO、マーチン・ソレルが先日、次のように話していた。「創造性で勝負する業界で忘れてならないのは、規模の不経済が存在することです。創造性豊かな社員を2倍雇っても、会社の創造性は2倍にはならないのです」
つまり、ステークホルダー(利害関係者)全員が享受できるだけの富と価値を生み出すには、このような逸材を雇い入れるだけでなく、彼ら彼女らの潜在能力が最大限に発揮しうる環境を整えなければならないのだ。
これは容易ならざる課題である。なぜなら、Aクラス社員を他の社員と区別する特徴を一つ挙げるとすれば、Aクラス社員はわがままを押し通したがるところにあるからだ。リーダーにすれば、まったく頭痛の種である。
この難問については、グローバリゼーションも逆効果でしかなかった。なぜなら、Aクラス社員の流動性がこれまでになく高まってしまったからである。つまり、彼ら彼女らの職場は、ボストンにもバンガロールにも北京にも用意されているのだ。