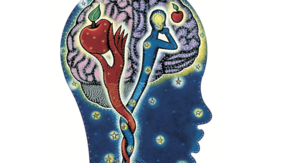-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
エビデンスを意思決定に活用する人は少ない
「本当に実効性のある治療法に関する最新かつ最善の科学知識に基づいて医療上の意思決定を下すべし」。これこそ、この10年以上医学界に一大旋風を巻き起こしてきた斬新な考え方、いわゆる「エビデンス(目に見える証拠)に基づく医療」(EBM:evidence-based medicine)である。
カナダ・オンタリオ州にあるマクマスター大学名誉教授、デイビッド・サケットがその提唱者である。彼の定義によれば、EBMとは「その時点における最善のエビデンスを、誠実かつ明示的、そして適切に用いて、個々の患者に施す医療上の意思決定を下すこと」である。サケットは、大学の同僚をはじめ、EBM運動に続々と賛同してきた医師たちと共に、信頼性が高く、臨床的にも有効な研究成果の選別と普及を目指して、またとりわけ重要な取り組みとして、これらの研究成果の応用に尽力している。
このように聞いて「笑止千万。そもそも医療上の意思決定の拠りどころとなるものにエビデンス以外ないではないか」と思われる向きは、これまでの医療の実態についてはなはだ認識不足といえる。
たしかに、研究成果は簡単に手が届くところにある。つまり、医療方法や医療用品に関する研究は、毎年何千件となく実施されている。しかし残念ながら、医師たちはこれらの研究成果をあまり活用していない。最近では、医師たちの意思決定のうち、エビデンスに基づいて下されたものは約15%にすぎないという調査もあるくらいだ。
医師たちはエビデンスの代わりに、たとえば学生時代に学んだ時代遅れの知識、検証されていない長年の慣行、経験の寄せ集めからなる行動パターン、己が信奉するお得意の治療法、製品やサービスを売り込むために群がる企業からの情報といったものに頼っているのだ。
企業の「病気」を治そうとする経営者たちの行動も医師たちのそれと何ら違いはない。それどころか、どの処方箋が信頼できるのかを見抜く眼力については、医師の足下にも及ばないのが現実である。しかも、信頼に足る処方箋を見つけ出そうとする意欲についてもしかりである。
仮に医師たちが、通常の企業経営のやり方に倣って医療行為を提供しようものならば、健康な人が病気になり、亡くならなくてもよい患者が死亡するという事態が増えることだろう。また、医療過誤が原因で刑務所に送られる医師、また罰則を科されるという憂き目に遭う医師も増加するだろう。
経営者たちも、そろそろ「エビデンス・マネジメント」に向けて動き出すべき時なのだ。とはいえ、たしかに経営には医療よりも難しい問題がいくつかある(囲み「エビデンス・マネジメントを妨げるもの」を参照)。
エビデンス・マネジメントを妨げるもの
もちろん、意思決定の質を改善するベスト・エビデンスは収集可能である。業界紙を読み、ビジネス書を買い、コンサルタントを雇い、専門家の話を聞きにセミナーに参加する。にもかかわらず、エビデンス・マネジメントの実践は難しい。次のような問題が障害となって立ちはだかるせいだ。
消化し切れない過剰な情報
ビジネスや企業経営にテーマを絞った雑誌や専門誌は、英語で書かれたものだけで何百種類にも上る。業界紙も何十とある。これまでに刊行されたビジネス書はおよそ3万点もあり、これに毎年、何千点もの新刊書が加わる。
さらに、ビジネス知識を提供するウェブサイトは『フォーチュン』誌や『ウォール・ストリート・ジャーナル』紙のオンライン版から、HRドットコムやガントヘッド・ドットコムのような専門サイトに至るまで、増加の一途をたどっている。
このような現状は、まさに消化し切れないほど過剰な情報に包囲されているといって差し支えない。しかも、利用しやすく、あるいは記憶しやすく整理されたうえで提示されていることは稀である。
たとえば、Business: The Ultimate Resource[注1]と題した超大作があるが、その重さは約3.6キログラム、特大の判型で2208ページもある。同書の説明によれば、この本は「ビジネスに携わるあらゆる組織や人々のOSとなるもの」だそうだ。
しかし、優れたOSはもれなくシームレスかつ論理的に組み立てられているものである。同書はもちろんのこと、これまでに刊行された百科辞典のような著作のなかで、この条件を満たしたものは1冊もない。
適切なエビデンスの不足
至るところにデータがあふれているにもかかわらず、信頼に足るものを追い求めているという状況はいまだ変わらない。
1993年、ベイン・アンド・カンパニーのパートナー、ダレル・リグビーは、さまざまな経営ツールや経営手法の効用と持続性に関して、我々が知る限り唯一の調査を実施した。同社が実施する「経営ツール調査」の最新結果は、同社が発行する機関誌、『ストラテジー・アンド・リーダーシップ』誌の2005年号に掲載されている。
そのなかでリグビーは、歯みがきやシリアルのような消費財ならば、適切な情報を入手できるが、企業が何百万ドルも投じて実施する施策については、ほとんど何の情報も得られないことは不思議であると説明している。
この調査は注目に値するものだが、それでも、さまざまな経営プログラムの利用度を測定しているだけであり、それらの価値については主観的な評価にとどまっている。
環境要件の不整合
一定条件の下でのみ成り立つアドバイスが障害になることも多い。ストック・オプションにまつわる議論を例に挙げよう。
エビデンスに基づいて考えると、ストック・オプションへの依存度を高めても、概して業績の向上には直結しない。予想利益の修正が必要になる可能性が高まるだけである。ただし、小規模で非公開の新興企業の場合には、ストック・オプションと成功が結びつくと考えられるばかりか、株価操作が招かれることも考えにくい。
また、保守的な研究姿勢、すなわち施策Aが成果Bを生み出すための環境要件を研究者が子細に明らかにすることは、信頼性の高い研究の証でもある。しかし残念ながら、その一方で、その研究結果が自社にふさわしいものかどうかという点について、経営者の判断を迷わせる原因にもなる。
わざと誤解に導く人々
よいアドバイスと悪いアドバイスを見分けるのは至難の業だ。それゆえ、何か欠陥のある経営手法を経営者に信じ込ませ、実施させようとする誘惑が後を絶たない。この手の問題は、コンサルタントによって引き起こされることが多い。
コンサルタントという存在は、仕事を獲得すれば確実に報酬を得られるが、優れた仕事が報酬につながるかどうかははっきりしない。経営改善に貢献できたかどうか、自己評価したところで報われることはまずない。最悪なのは、クライアントの問題の一部を解決しておけば、その後は芋づる式に次の仕事がコンサルティング会社に転がり込んでくることだろう。
我々の批判が手厳しすぎると感じるようならば、お気に入りのコンサルティング会社に、彼ら彼女らのアドバイスや経営手法の効果を実証するエビデンスについて尋ねてみるとよい。そして、そのエビデンスを吟味してみることだ。
みずからをあえて誤解に導く
サイモン・アンド・ガーファンクルの歌『ボクサー』に「人は聞きたいことしか耳に入れない。それ以外は無視される」というくだりがある、まさにそのとおりだ。企業経営に携わる者が、己の信条やイデオロギーと相容れない経営手法やそのエビデンスを無視することなどしょっちゅうである。ひるがえって、彼ら彼女らの経験的な知識のせいで、自分が見たいものだけ見ようとするのである。
これはきわめて危険だ。なぜなら、理論には「自己実現的」、すなわち自説に基づく行動そのものが自説を証明する方向に作用する性質のものがあるからである。たとえば、不信感を抱いた人の行動はつぶさに監視し、それが原因で信頼関係がいつまで経っても結ばれない。
逆に、権威者が自分のことを「不正行為を犯すに違いない」と決めてかかっているような状況では、実際に不正行為に手を染めてしまう人が少なくないというエビデンスが実験によって得られている。
効果を上回る副作用
エビデンスから判断して、何がしかの対策が明らかに正しく見えるかもしれない。実際には、その評価の視野が狭すぎる場合がある。この点に言及する際、我々がよく引き合いに出すのは、経営以外の事例であるが、公立学校における年齢による進級制度、つまり生徒の成績が合格水準に達していなくとも次の学年に進級させる制度に関するものだ。
99年の一般教書演説において、ビル・クリントン前大統領は多数派の意見を代表するかたちで、「履修すべき内容を習得していない子どもたちを進級させるのは本人のためにならない」と述べた。そして、ジョージ W. ブッシュ現大統領もこの意見を支持している。
しかし、これまでに発表された55件を上回る研究を見ると、年齢による進級制度の廃止は、功罪差し引きしても、マイナス効果のほうが大きいことが示されており、両大統領の信条は、これらの研究結果に反している。なお、この分野の信頼できる研究で、プラス効果を見出したものはない。
多くの地域の学校がこの制度の廃止に向けて動いたが、すぐに致命的な欠点が判明した。まず、生徒の進級を止めると、年長の生徒で学校があふれてしまう。また、生徒の平均在籍年数が延びることで、教師をはじめ、その他の経営資源への需要が増え、その結果、コストが急増した。また、落第した生徒は、いっそう成績を悪化させるばかりで、テストの点数は下がり、中退率が上昇した。
さらに、いじめの増加も報告されている。というのも、落第生たちはクラスメートよりも体が大きいうえに、落第させられたことに怒りを感じている。かたや教師たちは、生徒数が膨らんだ学級をまとめるのに手一杯となってしまうからだ。
ストーリーの説得力
巧みなストーリーのほうが効果的な場合も少なくない。このことを考え合わせれば、エビデンスに基づいて、非の打ちどころのない論証を重ねていく作業に専心するのはあまりにきつい。
もちろん、我々は「定量的データでなければ、エビデンスにあらず」などと考えてはいない。アインシュタインの言葉ではないが、「数えられるものすべてが重要なわけではなく、重要なものすべてが数えられるわけでもない」のだ。
ストーリーやケース・スタディも正しく用いれば、企業経営に役立つ知識を得るうえで強力なツールとなる。
たとえば、新製品開発に関する定量的研究は数多く発表されているが、技術者がどのように新製品を開発するのか、また経営者たちがどのように技術者(と製品)の成功を後押ししたり、逆に足を引っ張ったりするのかについて、トレーシー・キダーのピューリツァー賞受賞作『超マシン誕生』[注2] ほど、みごとに描写しているものは稀である。また、ゴードン・マッケンジーが書いたOrbiting the Giant Hairballは[注3]、企業の創造性を扱った書籍としては、我々の知る限り、いちばんおもしろくてためになる。
このように優れたストーリーは、エビデンスを踏まえつつも、たとえば何らかの仮説を提示する、定量的な研究を補足する、変化の影響を受ける従業員を鼓舞するといった面で貢献するという役割を果たす。
【注】
1)Business: The Ultimate Resource, Perseus Books Group, 2002. 邦訳は、2005年からダイヤモンド社より『世界で最も重要なビジネス書』『世界で最も偉大な経営者』など、分冊で刊行されている。
2)Tracy Kidder, The Soul of a New Machine, Little Brown & Company, 1981. 邦訳は、1982年にダイヤモンド社より刊行。
3)Gordon MacKenzie, Orbiting the Giant Hairball: A Corporate Fool's Guide to Surviving with Grace, Viking Adult, 1998.(未訳)
第1に、経営におけるエビデンスは、医療のそれほどには説得力に乏しい。次に、だれでも「経営のプロ」を自称できるばかりか、現実にそのように自称する向きが多い。さらに、よく引き合いに出される人物は、シェークスピアからビリー・グラハム(キリスト教伝道師)、ジャック・ウェルチ、トニー・ソプラノ(TVドラマの主人公)、戦闘機のパイロット、サンタクロース、アッティラ大王に至るまで、戸惑うばかりの幅広さである。