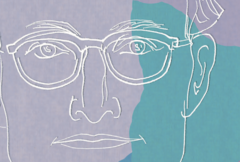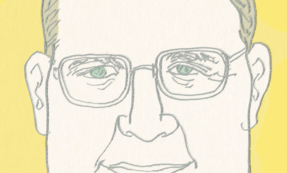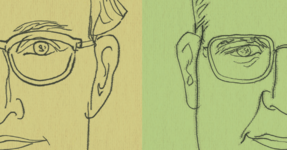-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
戦略論の時代の終焉
「戦略とは何か」と問われるならば、私はもはやそれを定義しようとは思わない。より正確に言うならば、こうすれば企業は成功する、あるいは事業がうまく発展するという、戦略と呼ばれる「型紙」、すなわち、経営学者の言うところのフレームワークでは、何も見えなければ、答えも出ないということだ。
競争優位の戦略、商品市場戦略、アライアンス戦略、そしてバリューチェーンやコア・コンピタンスといった、競争のエッセンスとなるフレームワークは、20世紀後半、安定成長が見込まれる工業化社会の末期に生み出されたものである。
それらを一部の企業エリートが学び、戦略なるものを立案し、数千あるいは数万の現場従業員たちを指揮しながら粛々と実践することで成長できる時代は終わった。
25年前、『企業参謀』(プレジデント社)を世に出し、マイケル E. ポーターやゲーリー・ハメル、あるいはクレイトン・クリステンセンらが洗練を重ねる以前に、日本に「戦略論」を持ち込んだのは私である。その人間の責任として、自らかつての「戦略論」に終止符を打ち、この新しい世界の進み方を考えてみたい。
隘路に迷い込んだ戦略論
なぜ、ポーターのポジショニングの概念やハメルのコア・コンピタンスの考え方、あるいはコンサルティング・ファームが編み出した数多の戦略論が機能しなくなったのか。
その理由は、我々はいま、かたちをとらえることができず、方向すらつかめない「見えない大陸」(The Invisible Continent)に入り込んでしまっているからだ。
『企業参謀』やその英語版『ストラテジック・マインド』(マグロウヒル社)において、私は企業戦略を3つのC("Customer" "Competitor" "Company")を用いて次のように定義している。
「戦略とは、顧客が求めているものに対する競争相手との相対的な力関係を、自社にとってよりよいものに効率よく変化させ、持続させるための計画や作業であり、その結果、競合企業に対する優位性が継続的に維持される」
対象とする市場や競合企業を明快に定義することが戦略の出発点であり、だからこそ、それらに対して何を目指し、どうすればよいのかといった"What"や"How"を論じる戦略論が有効に機能しえた。
しかし、この15年間で企業を取り巻く環境は激変した。もはや、戦略の前提となる自社の顧客や競合企業、市場を固定的に定義できる時代ではなくなっている。