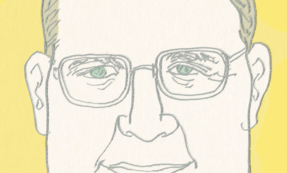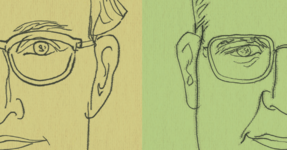-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
RBVに対するポーターの反応
前掲のマイケル・ポーターとジェイ・バーニーの両論文を読まれた方は「一体両者の対立点はどこなのか」と首を傾げられたかもしれない。この真相を理解するには、1990年代半ばのアメリカの経営学界へ立ち返らなくてはならない。
バーニーの91年の論文「企業リソースと持続可能な競争優位」[注1] や1986年の「戦略要素市場:期待と運、そして事業戦略」[注2] が徐々に注目を集め出した90年代初頭以降、「リソース・ベースト・ビュー」(以下RBV)の名の下に、これまで比較的分断されていた経営資源に関する研究群が一挙に統合される勢いを見せた。
アメリカ経営学界では、コア・コンピタンス経営、ナレッジ・マネジメントといった考え方も、RBVという文脈と共に理解され、欠くことのできない分野として確立した。
一方ポーターは、RBVの名を冠した論文が戦略分野に続々と登場するのを見ても、「RBVはオペレーション効率の向上を説明するにすぎない」という姿勢を一貫して崩さなかった。
実は今回のポーターの論文では、「リソース」(resource)という言葉は(おそらく意識的に)一度も使用されていない。同論文の「オペレーション効率」という項に、それをもたらすものとして「優れた技術、優れたインプット、十分訓練された従業員、または効果的な経営組織」といったものが列挙されているが、これらは皆RBVの文脈では「持続可能な競争優位の源泉」となりうるリソースである。
しかしポーターは、RBVで言うリソースとは「オペレーション効率を上げ、コストを削減するのみ」として限定的な解釈をする。ポーターによれば、売上げを増大させ新たな価値をつくり出すのは「リソース」ではなく、あくまで「戦略的ポジショニング」なのである。
ネット・エコノミーをめぐる相違点
両論文は次の点については認識が一致している。すなわち、「インターネットの発達によって情報の非対称性が解消され、取引の効率化がすべての市場参加者に同様の恩恵をもたらすため、そこから持続的競争優位を獲得することはより困難になる」ということである。両者の分岐点はこの後だ。
ポーターは「持続可能な競争優位の源泉は、コストを最小化するオペレーション効率の向上と、価値を創造する戦略的ポジショニングの組み合わせで達成される」と考えたうえで、インターネットは前者にはネガティブなインパクトを与えるが、後者の重要性は不変、という立場である。
前項で指摘したポーターのRBVへの認識を踏まえると、実はこのポーター論文は痛烈なRBV批判を含んでいることがわかる。すなわち、リソースがオペレーション効率の向上をもたらすのみである限り、「ネット・エコノミーの下では、RBVによって持続的競争優位を獲得することはいっそう困難になった」と言っているに等しい。
バーニーはRBVの代表的な研究者として知られるが、今回の論文タイトル「ニュー・エコノミー下で持続的競争優位は実現可能か? 答えはイエス」(原題)とは、このポーターの発したメッセージへの回答と言える。