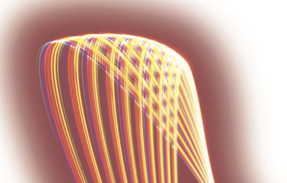-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
価格戦争は消耗戦
一人でも多く顧客を獲得しようと、競合他社をかわす戦略がさまざまに駆使されている。なかでも、価格を武器とするケースが増大しており、ちょっとした小競り合いが次第に価格戦争に発展してしまうのも、いまや日常茶飯事だ。
価格戦争は低価格で顧客を引きつけることを狙いとしているが、次から次へと報復的に価格が引き下げられていくと、最終的には業界全体の利益が急激に低下してしまうこともしばしばである。
1992年に起こったアメリカ航空業界での価格戦争が好例だ。アメリカン航空やノースウエスト航空をはじめとする各社は、どこかが航空運賃を下げると、競ってそれに合わせるか、いっそうの引き下げに走った。
その結果、航空機の輸送旅客数は過去最高を記録したが、同時に損失も過去最高となった。ある推計によれば、同年業界が被った損失総額は、航空業界が誕生してから稼いだ業界利益累計額を上回った、とすら言われている。
価格戦争が始まると、個人や企業、そして業界の利益が大きく犠牲にされる。経済的に大きな打撃を与えるにとどまらず、心理的にも弱気が蔓延していく。
だれが勝者になろうと、全員が全員、戦争が始まる前よりも悪い状況に置かれてしまう。
にもかかわらず、価格戦争はますます日常化しつつあり、その内容もこれまでになく激しくなっている。次の2つの例を見てみよう。
1|長距離電話料金
99年7月、スプリントは、夜間の長距離電話料金を1分間5セントにすると発表した。翌8月、MCIは、スプリントのオフピーク料金に合わせて料金を引き下げた。
同8月、今度はAT&Tが、消費者向け長距離電話事業の収益が下落していることを理由に、月額5ドル95セントの手数料で、平日休日を問わず24時間いつでも1分間7セントという新料金に値下げした。
この発表の日、AT&Tの株価は4.7%下落した。また、MCIとスプリントの株価も、それぞれ2.5%、3.8%値崩れした。