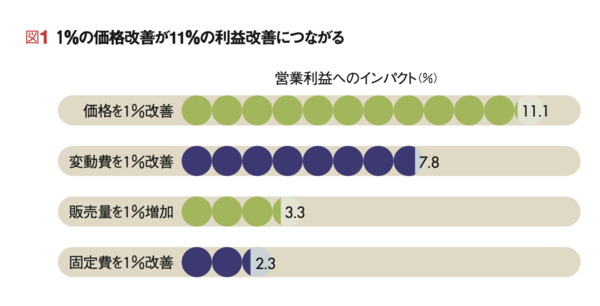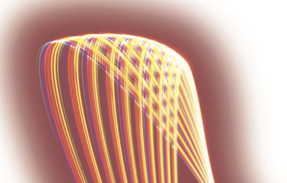-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
売上げを1%増やすか?
価格を1%上げるか?
利益を改善させたいならば、「プライシング」こそ、最もインパクトのある方法だろう。つまり、リベート等を含む価格体系にメスを入れ、戦略的に設定するのである。
これは、洋の東西を問わず、多くの企業で死角となっている分野であり、しかも手をつけにくいため放置されやすい。「経営がうまい」と称される企業ですら、往々にしてプライシングは聖域であり、「顧客との関係が悪化するのではないか」「顧客を失うのではないか」と恐れて、だれも進んで取り組もうとはしない。
しかし実は、プライシングを見過ごすことで被る機会損失はきわめて大である。逆に、一度取り組めば、効果てき面である。プライシングが適正であると、販売量を増やすよりも、利益に貢献する。裏を返せば、プライシングが適正でなければ、たちまち利益を損なうはめになる。
プライシングとは、1ドル、1セント単位の業績を左右する、いわばビジネスの「イロハのイ」だ。基礎的かつ致命的なマネジメント・スキルの一つと考えなければならない。
では、価格を適正化することで、どれくらいの改善効果が得られるのだろうか。たとえば、販売量を1%増やした場合と価格を1%上げた場合を比較してみよう。
平均的な企業では、価格をいじらずに販売量が1%増加した増合、営業利益は3.3%改善する。一方、販売量が減らないと仮定したうえで、価格を1%引き上げた場合、営業利益は11.1%も改善する(図1「1%の価格改善が11%の利益改善につながる」を参照)。
結果として、プライシングには、販売量を増加させた場合と比べて、だいたい3~4倍の利益改善効果があることがわかる。
別の例も挙げておこう。ある耐久消費財メーカーは、全商品について価格を2.5%上げただけで営業利益が30%近く増大した。また、薄氷を踏む思いで価格を3%上げたところ、営業利益が35%改善したという産業機器メーカーもある。これらはプライシングによる効果が顕著に表れたケースである。
マッキンゼー・アンド・カンパニーが調査したところ、消費財、エネルギー、銀行や金融サービス業など、広範な業界でも同様の結果が得られた。以上のことから、商品開発やマーケティングと等しく、プライシングにも努力を傾けるべきであり、継続的に改善を心がける必要があると明言できる。