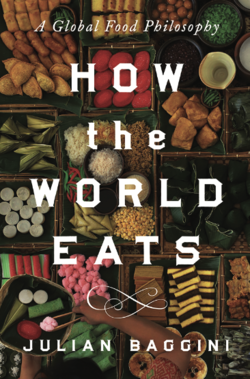-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
少ない資源で多く生み出すために
著名な哲学者、ビル・ゲイツお気に入りの科学者、調査報道ジャーナリスト、非営利団体の創設者が、同じ時期に同じテーマの本を執筆するとなれば、極めて重大かつ複雑な問題であり、早急な対応が必要なのは明らかだ。
現代の崩壊したグローバルな食糧システムにおける厳しい現実を考えてみよう。米国人の40%が肥満である一方、アフリカ人の20%が栄養失調だ。世界全体で1人当たり1日3000キロカロリーを供給できるだけの食糧が生産されているが、その3分の1が無駄になっている。農場や家畜施設は、気候変動の脅威にさらされながら、その原因である大気中の二酸化炭素の多くを排出している。
2050年には82億人に達する人口を支える唯一の方法は、食糧生産を増やし、より均一で効率的な流通を確保することだと、専門家は指摘している。しかし、地球を救うために、農業界は環境への影響も「同時に」かつ劇的に減らさなければならない。ここで厄介な問題が生じる。地球の存続がかかっている状況で、より少ない資源でより多くの生産量を生み出すにはどうすればよいのか。
「共通の原則」を出発点にする
英王立哲学研究所の元学術ディレクターでHow the World Eatsの著者であるジュリアン・バジーニは、まず共通の原則に立ち返る必要があると主張する。そして、東アフリカのマサイ族や北極圏のイヌイット、アルゼンチンのガウチョ、ブータンの小規模農家、中国の市場商人、オランダの農業企業経営者など、さまざまなコミュニティと地域に根差した食文化を紹介しながら、私たちが食べたり飲んだりするものの生産、加工、流通、消費しなかった分の廃棄に用いるシステムの多様性と複雑さを描いている。
現在の「食の世界」が、人間(「文字通り、そして比喩的にも、ある者は太り、ある者は飢えている」)や環境(「あまりに多くのものを投入して(中略)あまりに多くの有害なものを排出する」)に害を与えるだけでなく、動物にとって多くの農場が「生き地獄」になっている現実をバジーニは指摘する。しかし、たとえば牛肉を食べない食生活といった多くの解決策は、有効な地域もあれば、そうではない地域もあると言う。