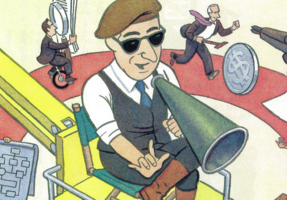-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
大型合併はグローバル戦略に適しているか
多くの経営者は「グローバル経済において、最も有効な戦略は、企業規模を拡大することである」と考えているようだ。それを証明するかのように、『ウォール・ストリート・ジャーナル』や『フィナンシャル・タイムズ』の一面では、連日のように大型合併の記事が躍っている。
これらの合従連衡はかつてないスピードで、しかもグローバルに、そこかしこの業界で起こっている。
石油業界では、まずエクソンとモービルの合併が代表的だ。また、アモコと合併したブリティッシュ・ペトロリアム(以下BP)は、続けざまにアトランティック・リッチフィールドとも合併した。
自動車業界ではダイムラーベンツがクライスラーと合併し、フォード・モーターはボルボの自動車部門を買収した。また、ルノーは日産自動車を傘下に収めた。
同様の合併劇は、通信、エンタテインメント、金融、飲料からセメントに至るまで、さまざまな業界で見られるようになった。
このような大型かつ巨額のクロスボーダーM&Aが進行している背景には、各国の市場がグローバル化するにつれて「業界内の寡占化は避けられない」だろうという、共通認識がある。そして、市場を掌握できるのは、選ばれたごく少数のプレーヤーだと予想されている。
そのような優位な立場にある企業は、製造やR&D、ブランド等において「規模の経済」をさらに働かせる必要を感じている。すなわち、規模の経済をテコに、潜在的なライバルを威嚇して追い払い、新しい市場の主導権を握ろうというわけだ。
この視点から見れば、クロスボーダーなM&Aは企業の盛衰を分ける大問題である。生き残りたければ、ましてや成長したければ、その業界において世界最大のプレーヤーにならなければならない。
この考え方はいまに始まったものではなく、長きにわたる系譜がある。
100年以上前、カール・マルクスは「一人の資本家は常に多くの資本家を滅ぼす」と記している。この言葉が意味するところは、激しい競争を経ていくうちに一握りの資本家に次第に絞られていき、いずれ彼らがすべてを独占するということである。