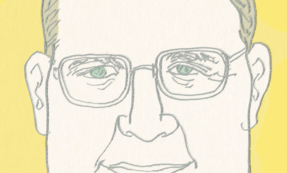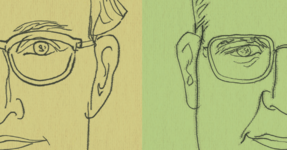-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
ヤフーに戦略はあったのか?
1994年の創業以来、ヤフーはニュー・エコノミーの「ブルー・チップ」(優良株)の一つとして急成長を遂げてきた。インターネット最大のポータルサイトとしては、驚異的な実績──1日当たり1億人のビジット数、200%近い年間売上高の成長率、ウォルト・ディズニーを上回る株式時価総額──を上げている。「デジタル時代の花形企業ともなれば、このようなものだろう」と当然視されるようになった。
ヤフーは、通常我々がインターネット企業には期待しないものを生み出している。それは「利益」である。先例を見ないほどのヤフーの成功ぶりは、周知の事実だ。だが、その勝因を従来型の市場戦略の考え方で説明するのは難しい。
たとえば、ヤフーの成長を「市場そのものが魅力的だったから」と一言で片づけるわけにはいかない。実際、インターネットのポータル分野は、戦略家にとっては最大の悪夢といった状況にある。その特徴と言えば、熾烈な競争、瞬時に模倣してしまう競合他社、そして一銭も払おうとしない顧客。さらに始末が悪いことに、参入障壁もないに等しい。
かと言って、ヤフーの成功は、その経営資源が独自性や高付加価値を備えていたわけでもない。設立時には、コンピュータと強力なアイデア以外何もなかった。
では、戦略はどうだったのか。アナリストの多くは、ヤフーに戦略があったのかどうかすら定かではない、と言うだろう。同社は、ウェブサイトを言わばカタログのように集めたサイトとしてスタートし、次にコンテンツをまとめたサイトへ、やがてはユーザーのコミュニティへと発展していった。最近はメディア、eコマース(電子商取引)およびコミュニケーション・サービスの広範なネットワークとなっている。仮にヤフーに戦略があったとしても、従来の教科書的な観念でそれを特定するのは非常に困難だ。
シンプル・ルールでニュー・エコノミーのチャンスをつかむ
ヤフーのサクセス・ストーリーは劇的ではあるが、こうした事例はまだある。ニュー・エコノミーでは、これ以外にもイーベイやアメリカ・オンライン(以下AOL)など多くの企業が、従来のモノサシで測れば魅力に乏しい市場領域で、その戦略を進化させることによってトップに躍り出ている。
また、これはニュー・エコノミーに限られた現象ではない。伝統的な産業分野の企業も、優れた経営資源や戦略的ポジショニングといった優位性がなくとも、他社に差をつけてきた。エネルギー分野のエンロンとAES、鉄鋼分野のイスパット・インターナショナル(以下イスパット)、セメントのセメックス、通信分野のボーダフォンとグローバル・クロシングなどである。
ごく普通の産業構造、何の変哲もない経営資源、そして常に進化する戦略──こうした環境にもかかわらず、このいずれの企業も立派な業績を上げている。このため、きわめて重要な疑問が浮かんでくる。
これらの企業はいかにして成功したのだろうか。言い変えると、目まぐるしく変転し続ける市場にあって、その優位性はどこから生まれるのか。ニュー・エコノミーにおける戦略とはどのような意味を持つのか。
ヤフーなどの成功の秘訣は「シンプル・ルール戦略」である。これらの企業は、競争優位性を得る最大のチャンスは、市場の混乱に潜んでいることを知っている。このため、混沌とした市場にあえて飛び込み、チャンスを探り当て、市場進出に成功し、そして状況に応じてチャンスからチャンスへと柔軟にシフトする。