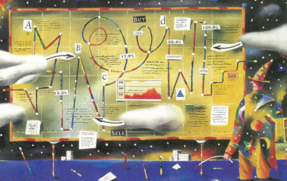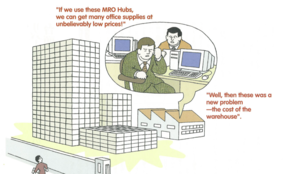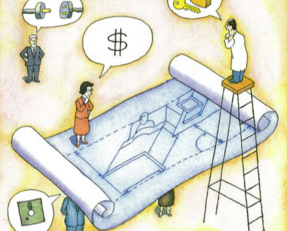-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
いまやメーカーの「ドル箱」は川下事業
1990年代は、アメリカの産業界にとって「繁栄の10年」だった。しかし、そのようななかでも、製造業だけが、その恩恵に浴することができなかったのはなぜか。
たしかに、景気は長期にわたって拡大し続けていたし、企業は生産性を高めて品質を改善しようとそれこそ身を削るような努力も重ねてきた。にもかかわらず、この10年間、大手メーカーは軒並み苦戦を強いられてきた。
たとえば、ワールプール、テキサス・インスツルメント、ポラロイド、ボシュロムといったおなじみの巨大企業にしても、利益の伸びはマイナスか、かろうじてプラスといったところだった。
結果として、数多くのメーカーが、同じような苦しみを味わっているわけだが、株式市場が全体として高値に沸くなかで、製造業銘柄だけはどうにもパッとしなかった。
大手メーカー1000社を対象に、88年以降の株価データを調べたところ、「S&P500」(スタンダード・アンド・プアーズ総合500種株価指数)よりも高水準を維持しているのは、わずか8社に1社であり、実に「3社に1社」が長期低迷にあえいでいる。
しかしそんな「土砂降り」のなかでも、ごく一握りとはいえ、気を吐くメーカーがある。
ハネウェル、ゼネラル・エレクトリック(以下GE)、ノキア、コカ・コーラなどがそうで、売上げ、利益、株価のいずれを取り上げてみても、その伸びは順調だ。
業種こそさまざまだが、これらの「猛者」たちは、ある共通点で結ばれている。つまり、いずれも「従来型のモノづくりが中心の川上事業」ではなく、「サービスや流通といった川下事業」に重点を置いた顧客志向型経営によって、繁栄を謳歌しているということだ。
これらの企業には、製造業におけるケイパビリティ(実行能力)を基盤としつつも、ひたすらモノづくりに明け暮れるのではなく、製品のライフサイクル全体を視野に入れて「付加価値の創造」に乗り出しているという大きな特徴がある。
では、一部の賢明なメーカーが川下事業に注力し始めたのはなぜか。それは、「利益が上がる」というきわめて単純な理由からだった。需要が全般的に伸び悩んでいるため、製造と販売を主体とする従来型のバリューチェーンからは、おいそれとは利益を搾り出せなくなったのである。