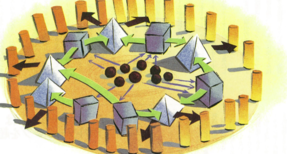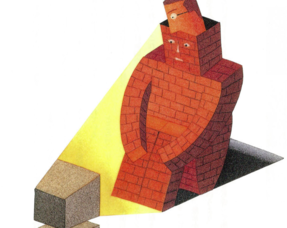-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
ロイヤルティ重視はeコマース経済の必然
eコマースについて考えようという時に、「ロイヤルティ」という言葉を真っ先に思い浮かべる人はまずいないだろう。むしろ、古風な響きを持つこの言葉と、マウスのクリック一つで顧客がついたり離れたり、抜け目のない輩がより有利な取引を求めてデータベースを洗い直したりするような世界と、どこでどうつながるのかと不思議に感じるのが普通だろう。
インターネットのグローバル市場は匿名性の世界であり、村社会の良識が何の役に立つのか、ロイヤルティなんていう美徳は、いまや絶滅の危機に瀕しているではないか、という声が聞こえてきそうだ。
しかし、事実は正反対である。eコマースの最先端を走る経営者は──デルコンピュータのマイケル・デルからイーベイのメグ・ホイットマン、バンガード・グループのジャック・ブレナンやW. W. グレインジャーのリチャード・カイザーまで──だれもが顧客の維持に心を砕き、オンライン事業の命運を左右する問題として認識している。
彼らは、ロイヤルティ重視が経済的必然であることを熟知している。インターネットによって顧客を獲得するには巨額の費用が必要であるうえに、獲得した顧客が頻繁にサイトにアクセスし、何年にもわたって自社商品の購入を繰り返してくれない限り、利益は極端に低いままだからだ。
また、ロイヤルティ重視が競争上の必然であることも承知している。ウェブの潜在力を活用して、顧客に特別の付加価値を提供する方法を考え出す企業は、どんな産業においても現れる。彼らが、出遅れたライバルを尻目に、多大な利益増につながる顧客の囲い込みを図るのは当然だからである。
ロイヤルティという接着剤なしには、最も優れたeビジネスモデルでさえ、崩壊の憂き目に遭うことも考えられるのだ。
この2年間、我々はベイン・アンド・カンパニーの同僚と共に、eロイヤルティについて研究を重ねてきた。多くの大手インターネット企業の戦略と慣行を分析し、それらのウェブサイトをデザイン面と機能面から評価し、サイトの顧客数千人に対して調査を行った。
その結果、驚くべき事実が明らかになった。「ウェブ上の顧客は移り気で飽きっぽく、つねに新しいアイデアに飛びつく傾向がある」という一般的な認識とは大きく異なり、実際にはB2C(消費者向け)でも、B2B(法人顧客向け)でも、ウェブは非常に結びつきの強い性質を持った場なのである。
今日のオンライン顧客のほとんどは、明らかにロイヤルティ志向を示しており、ウェブのテクノロジーは、それを正しく使用すれば、顧客ロイヤルティを強化する役に立つ。
既存顧客のなかで利益貢献度の高い人々のロイヤルティを得るのにもたついたり、望ましい新規顧客を獲得することができなかったりでは、価格に敏感に反応するタイプの顧客の要求に振りまわされる、という惨めな状況に陥ることになるだろう。