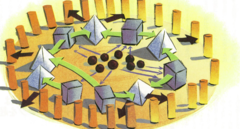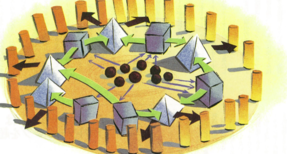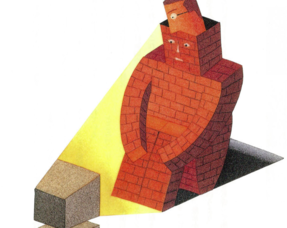-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
「コストの透明性」の脅威
eコマース(電子商取引)がもたらす可能性に、みな酔いしれているように見える。
たとえば、消費者は商品が安くなり、ショッピングも楽になると期待している。投資家はネット関連企業のIPO(株式公開)でひと儲けしようとたくらんでいる。新興企業は自社のビジネスモデルで業界が様変わりすることを夢想する。こんな具合だ。
ところが企業にすれば、インターネットは史上最大の「脅威」でもある。可能性の背後に隠れた厳しい現実に気づけば、酔いもたちまち醒めることだろう。インターネットによって、その重要な能力──すなわち、商品のブランド力を強化する能力、消費者にプレミアム価格を支払わせる能力、そして高い利益率を確保する能力──は危機にさらされているのだ。
インターネットを使うと商品やサービスの価格を容易に比較できることは、いまやだれでも知っている。ところが、これは一面にすぎない。事ははるかに深刻である。
真の脅威は、経済学者が「コストの透明性」(cost transparency)と称するものだ。これは、インターネットでは豊富な情報を簡単かつ無料で手に入れられることに端を発した現象である。インターネット上の情報のほとんどが、コストの透明性を高める役割を果たしている。
言い換えると、このような情報のおかげでコスト構造が「丸見え」になり、値札が示す価格はコストと比較してはたして妥当なのかどうか、一消費者でも判断できるようになったのである。
なぜ、そうなるのだろうか。これを理解するために、まずインターネットが出現する前の状況で考えてみよう。
少し前のことだが、プライベート・ブランドがナショナル・ブランドの市場シェアを侵食し始めた。そのきっかけは、プライベート・ブランドの品質が向上したことにある。消費者はナショナル・ブランド並の品質の商品をはるかに安く買えることに気づいた。
プライベート・ブランドは消費者たちにある重要な情報を与えた。それは「ナショナル・ブランドのメーカーはコストにかなりの金額を上乗せした高い価格を付けている」というものだ。
コーンフレークの例を見ると、プライベート・ブランドはナショナル・ブランドよりも1箱2ドル安く買えるばかりか、味も大差ない。消費者たちは「高価格ブランドの製造コストは思っていたより低いのだ」と想像した。