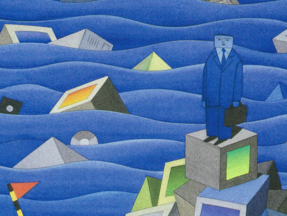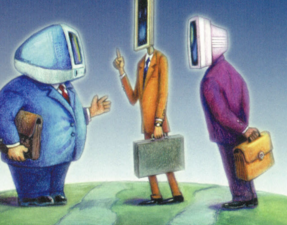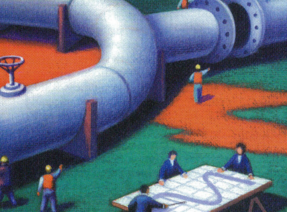-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
業務プロセスの統合は階層組織ではうまくいかない
最近、なりふり構わず合理化を進める企業が、その外聞を取り繕うために「リエンジニアリング」という言葉を持ち出す例が見られる。しかし、真にリエンジニアリングを成功させた企業には、次のような数多くのメリットがもたらされる(注1)。
・事業運営のスピードアップと効率化を可能にし、ITの効用をいっそう引き出す
・従業員の権限を増大させるとともに、自分自身の仕事が会社全体の中でどのような位置づけにあるのかを深く理解させることができる。ひいては、各人の仕事ぶりにプラスの変化をもたらす
・品質を向上させ、また、打てば響くようなサービスを実現することで、顧客の愛顧に応えられるようにする
・コスト低減や収益向上、株価上昇などを可能にし、配当にも寄与する
これら諸点もさることながら、リエンジニアリング最大の功績は、トップ・マネジメントに発想の転換を促したことである。かつて企業とは、明確な役割を与えられた独立組織の集合体と見なされていた。しかし現在では、このような組織観は影を潜めている。
代わって台頭したのは、数多くの仕事の流れと情報の流れの中から、その時々で関連性の高いものをひとまとめにしたのが「組織」である、という考え方だ。そこでは、仕事や情報が社内の組織的枠組みを超えてヨコ方向に行き交い、最終的には顧客接点に集約されていく。
つまり、リエンジニアリングがもたらす恩恵によって、経営者は表層的な組織構造に惑わされることなく、「顧客に価値をもたらし、かつ株主の利益を創造する」という、企業の基本目的に目を向けられるようになったのである。
しかし、このような業務プロセス重視の組織観はいまだ十分に実現されているとは言い難い。多くの企業が、付加価値を生まない事業活動を切り捨て、関連分野ごとに事業活動を再編し、「コア・プロセス」(主要な業務プロセス)の統合を推進してきた(注2)。
とは言うものの、組織管理手法にまで踏み込んで、抜本的な変革に取り組んできたかと問えば、そのような事例は少数にとどまる。どの企業でも、たいていは地域別や製品別、機能別のヒエラルキー組織が依然として根を張り、それぞれの組織が「仕事やスタッフ、経営資源などを手放してなるものか」と身構えている。