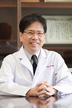-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
体の至るところで持続する腫れやむくみを繰り返す難病「遺伝性血管性浮腫」(HAE)。希少疾患であるゆえに、認知度の低さや診断に求められる専門性の高さから診断に時間を要することが知られており、日本では初発から診断まで平均で14年近くかかっているとされる。
その間、患者は時に生命の危険を来す可能性があるこの疾患に苦しみ続けることになる。そこで、HAEと診断されずに苦しむ患者を救うために、医療従事者・患者団体・学会・製薬企業・IT/MedTech(メドテック)企業などが連携し、早期診断と診断率向上を目指す「遺伝性血管性浮腫診断コンソーシアム」(英名: Diagnostic Consortium to Advance the Ecosystem for Hereditary Angioedema、略称:DISCOVERY)が2021年2月に設立された。
同コンソーシアムの設立意義や活動の方向性について、代表理事を務める秀 道広氏(広島市立広島市民病院 病院長)と堀内孝彦氏(九州大学病院別府病院 病院長)に、コンソーシアムの設立と運営を支援してきたデロイト トーマツ コンサルティングの2人が聞いた(座談会はオンラインで行った)。
DISCOVERYは協創のプロトタイプを目指す
荒見 秀先生も堀内先生も、HAEの治療や研究活動に注力しながら同時に幅広い疾患領域、あるいは産官学の枠を越えた活動を広く続けておられます。これまでの活動について簡単にご紹介いただけますか。
秀 私は、免疫アレルギーの中でも特に、じん麻疹、アトピー性皮膚炎の臨床と研究に取り組んできました。HAEについては、初めから取り組もうと思っていたわけではなく、目の前に現れてくる患者さんや未解決の問題を投げ出さずに取り組んでいく中で、気がついたら、いまみたいになったというのが実情ですね。
HAEに関心を持ったのは、血管性浮腫という、じん麻疹でもよくある症状を起こすことからです。じん麻疹、アトピー性皮膚炎という、ありふれた、でもなかなか治らない病気の患者さんと向き合い、社会活動や疾患を通して出会った人たちとの交流を続けていくうちに、活動の場もだんだん広がっていきました。
患者さんは、一人ひとりかけがえのない存在です。その人たちに対して、自分がやるべきことにできる限り注力していくと、課題は途絶えることなく出現し、いまのような形になったということです。

広島大学医学部卒。米NIH(国立衛生研究所)研究員、英ロンドン大学セント・トーマス病院研究員などを経て、2001年広島大学医学部皮膚科教授、2016年広島大学医学部長、2020年広島大学副学長。2021年4月より現職。遺伝性血管性浮腫(HAE)の患者同士の交流や医療関係の情報交換など、患者や家族が健康に楽しく暮らしていくことをサポートするために設立したNPO法人「HAEJ」の協力医師として、その活動に精力的に従事。また、希少性難病の患者の病気や日常生活に関する情報を収集し、研究を進めるためのオンライン研究プラットフォーム「RUDY JAPAN」におけるHAEの研究に参画。「遺伝性血管性浮腫診療のためにWAOガイドライン」の翻訳に携わるなど、HAEに関係して幅広く活動。
堀内 私は免疫疾患、特にリウマチと膠原病を専門にしています。これらの疾患は、私が医者になった当時は難病といわれていて、治療法もステロイドぐらいしかありませんでした。そうした難病の人たちのために何かできないかと思い、自分の専門を決めました。難治性疾患の治療ではいま、九州大学で強皮症の造血幹細胞移植に取り組んでおり、保険適用まであと一息のところまで来ました。
基礎的な研究では、腫瘍壊死因子(TNF)*1に関する研究をしています。留学中から補体*2の研究もしています。HAEについては、難病であることと補体との関係が深いことから興味を持ち、研究を続けています。
荒見 医療従事者として目の前の患者さんと向き合い続けることで新たな課題を見つけ、その解決に粘り強く取り組まれてきたわけですね。取り組む人が少ないHAEにお2人が踏み込んだのには、何かきっかけがあったのでしょうか。
堀内 HAEの患者さんを紹介されて、自分が診るようになったことが大きいですね。基本的に私は、患者さんを全体として診たいという思いを持っています。同じ内科でも、消化器、循環器など、臓器別に特化した診療科が多い中、リウマチ、膠原病は、患者さんを全体で診なくてはなりません。
同様にHAEも、1カ所だけでなく、全身にさまざまな症状が出るのが特徴です。患者さんを全体として診たいという点でつながっている気がします。

九州大学医学部卒。国立がんセンター研究所研究員、米アラバマ大学医学部フェローなどを経て、2008年九州大学大学院医学研究院准教授、2013年九州大学病院別府病院教授、2016年4月から同病院長を併任。専門は臨床免疫学、リウマチ学。「血管性浮腫」の実態を解明してその成果を社会に役立てることを目的として設立したNPO法人「血管性浮腫情報センター」(略称:CREATE)の代表として活動するとともに、「HAE患者会 くみーむ」にて患者とその家族のサポート活動に精力的に従事。また、日本補体学会が作成する我が国の「HAE診療ガイドライン2010年初版、改訂2014年版」の作成に責任者としてかかわった。「改訂2019年版」では再び責任者として厚生労働省研究班と連携・協力し、我が国のHAE診療ガイドラインを作成。アジアで初めてHAE3型の原因遺伝子を同定した。
荒見 なるほど、全体として診るということは、患者さんを治療するだけでなく、早く診断できるようにしたり、治療において医療費助成が受けられるようにしたりするなど、患者さん目線で、患者さんが抱える課題に向き合っていくということですね。
堀内 そうですね。なかなか診断がつかないことに加え、この病気には遺伝性というセンシティブな側面、また薬が比較的高額であるという課題もあります。そういったさまざまな課題に対して、広く関わっていかなくてはならない病気だと思います。
荒見 DISCOVERYは、早期診断の促進という難題に対して、業界横断での施策をより広く、スピード感をもって推進すべく設立されました。お2人は共同で代表理事を務めておられますが、この取り組みのどのような点に賛同し、参画されたのでしょうか。
秀 HAEという病気にとって、よりたくさんの人が参画して、よりたくさんのリソースがこの活動に使われるということは好ましいですし、それによって多くのものが生まれてくると思います。数の力というのはいろいろな面で重要です。特に患者さんがたくさん集まってくれば、少数ではわからなかったことがわかるようになり、学問が大きく進歩します。それから、社会に対する発言力も大きくなります。
日本がかつてエレクトロニクスの分野で世界のトップを占めていたころ、国内のいくつかの企業のエンジニアたちは時々集まって、情報交換をしながら、競争と協創によって大きな成果を上げていたそうです。それはとてもよい成功例で、DISCOVERYの中でも、同様の相乗的な効果が生まれることを期待しています。
堀内 私は、非常に面白い取り組みだと思って参画しました。つまり、民間企業とか、患者さんの団体、あるいは医療従事者とか、さまざまな人たちが集まって、早期診断という一つの目的に対して、一緒に取り組むのは面白いと。
たとえば、リウマチ、膠原病の場合でも、いろいろ薬が出ていますが、競争している企業同士が協創する例は知りません。ですから、DISCOVERYの取り組みが一つのプロトタイプになって、ほかの領域にも広がっていくといいなと思っています。
荒見 おっしゃる通りこのような取り組みは、特に日本においてはユニークです。HAEの領域でも先生方をはじめとして、医療従事者・患者団体・製薬企業の皆様が各々の専門性をもって患者さんのためにこれまでも尽力されてきました。
DISCOVERYはそのような従前の取り組みを否定するのではなく、むしろ時に競争環境に置かれつつも「早期診断の促進」という社会課題の下に手を取り合うという、まさに競争から「協創」へのシフトを体現しています。我々は、業界内外の皆様が有する能力や知見、経験を共有できるスキームを構築し、継続的に運用していくことが、患者さんとご家族に対する提供価値の最大化、早期化に資すると考えています。