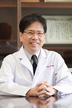違いを受け入れ、尊重し、協業することで、
新しいものを生み出す
荒見 DISCOVERYが成功し、こういった取り組みがうまくいくことを発信できると、希少疾患全体、あるいはライフサイエンス・ヘルスケア業界に大きなインパクトを出せるはずです。先生方はこの活動を通じて、どのようなアウトカムやインパクトを期待しておられますか。
堀内 まずは、このミッションを成功させて、それと同時にプロトタイプとして波及させたいですね。できれば、行政も巻き込んでいきたいのですが、そのためには、学会の力、患者団体の力、製薬会社の力など、いろいろな力が揃ったほうがやっぱり強い。日本ではいままで、まとまった力を発揮できるような組織がなかったわけですが、DISCOVERYがうまくいって、行政を動かすことができたら、同じような取り組みが広がっていくのではないかと非常に期待しています。
秀 新しいテクノロジーによって、いままでできなかったことができるようになることも大切だと思います。そういう意味で、いまやろうとしているビッグデータの解析などは、非常にチャレンジングで期待しています。
田尾 おっしゃる通り、DISCOVERYの特徴は、デジタルテクノロジーを積極活用しようとしている点です。特に電子カルテやレセプトデータから診断アルゴリズムを構築し、診断に活用していくこと、またDoctor to Doctor(医師同士)の遠隔相談スキームなどは日本ではまだスタートしたばかりの領域ですし、デジタルメディアを活用した疾患啓発・早期診断は業界の枠を超えた知見が求められます。このような先進的な取り組みについてDISCOVERYで成功事例をつくれると、他の疾患領域への拡大など、より医療の世界に大きなインパクトを残せるのではないかと思います。
もう一つのDISCOVERYの特徴は、バックグラウンドやケイパビリティが異なる多様なステークホルダーとの協業を前提としている点ですが、どのようなやりがい、難しさを感じておられますか。また、協業するうえで大切にしておられることはありますか。

ライフサイエンス&ヘルスケア シニアマネジャー
主に製薬企業に対する全社トランスフォーメーションや、デジタル・トランスフォーメーションをエンド・トゥ・エンドで支援している。また、近年は、患者向けのソリューション構築・展開も手がけている。
堀内 大切にしているのは相手への信頼と敬意です。いろんな人が集まって協働するわけですから、信頼できる人でなければ一緒に仕事はできないし、互いに尊重し合うことを積み重ねることでうまくいくのだと思っています。
それと、同じ目的を共有することです。自分の願望や都合よりも目的の達成を優先し、自己犠牲もいとわない人が集まれば協働がスムーズに進むし、大きな成果も得られるのではないでしょうか。
今回のプロジェクトでのやりがいは、私が知らない方法で疾患へのアプローチができるようになることですね。AI(人工知能)を活用しての早期診断などは、大学の中にいて、小規模の予算でやっていたら絶対に学ぶことも触れることもできません。
秀 正直なところ時間をやり繰りするのが大変ですが、それ以上に得るものがあると思います。忍耐も要るし、工夫も要るし、適正な資源の配分の仕方も必要ですよね。その辺りはやりがいでもあり、とても大変なところでもあります。
中でも私が大切にしたいのは創造性ですね。HAEは、本当によくわからない病気です。だから、患者さんとの接点の中で、常に新しい発見があります。遺伝子の異常がわかったらゴールというのではなく、それからどうするかが課題です。ですから、みんなで一緒に活動することによって気づきを得て、新しいものを生み出すことが大切だと思っています。
荒見 創造性という点で、工夫されてきたポイントはありますか。

ライフサイエンス&ヘルスケア マネジャー
製薬企業のR&D部門でCMC研究・知財管理・新規事業開発に従事後、現職。入社以来一貫して医療業界の企業・アカデミアに対する戦略立案・実行支援に関わり、近年はクロスボーダー/デジタル変革も手がける。
秀 自分の知らなかったことを患者さんは教えてくれるので、それを聞き出したい、知りたいと、こちら側が興味を持って接することです。それから製薬企業や行政の人も、病気の現場に触れることで初めて気づくことがたくさんあるはずです。そこから、いままでできなかったことができるようになったり、わからなかったことがわかるようになったりします。そういう多くの気づきをつなげていけたらいいなと思いながら仕事をしています。
こうした取り組みに関わっている人たちは、目的は同じでも、思惑や求めるものは少しずつ違います。たとえば、研究者は社会から注目されるような研究をして、論文をたくさん出せるとすごく嬉しい。
我々医師は、患者さんの病気をよくしたいという思いが一番ですが、そのために新しいことがわかるとか、できるようになるとか、そういったことにも大きな価値を感じています。
田尾 それぞれが違うからこそ難しい部分もある一方で、違うものが組み合わされることによって、より大きく羽ばたける可能性も秘めていると思います。そして、DISCOVERYが成功するカギとしては、参画している各ステークホルダーが目的に共感していることはもちろん、それぞれの観点でベネフィットを享受できる関係性をつくり上げていくことだと思います。そうすることによって、より大きなインパクトを、持続的に提供していきたいですね。