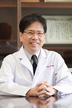早期診断を実現したうえで、治療も含めた医療体制の構築が必要だ
荒見 HAEに関わる中で、どういうところに難しさを感じていらっしゃいますか。
秀 じん麻疹が原因で、亡くなることはまずありません。病気が悪化して、眠られなくなるほど苦しむことはあっても、死ぬことはない。しかしHAEは、死に至ることもあれば、本当にのたうち回るほどの苦痛を味わうこともある大変な病気です。臨床医になった以上は、やはりそうした大変な病気の治療に携わりたいという使命感を持ち、やりがいも感じます。
診断に至る難しさもあるのですが、診断してからどうするかということも難しいです。薬はいくつかあるものの、使い方はまだ十分確立されていません。適正な使い方は、自分たちで創造していくしかない。しかも、一回の治療にかかる薬代が非常に高い。そのため、診断を受けてから、どういうふうに治療していくか。根本的には治せないとしても、どう薬を使い、生活を組み立てていけばいいのかが、患者さん一人ひとり違うところが、やはりこの病気の難しいところだと思いますね。
堀内 HAEに対する薬の使い方はすごく難しいと思います。もともとHAEという病気は、補体の「C1インヒビター」の欠損のみが原因だと思われていたのですが、実はそれ以外の病態の方々もいることが2000年以降わかってきました。
なので、一口にHAEと言っても治療法はさまざまで難しいのです。
田尾 今後、HAEの診断、あるいは診断後のチャレンジを超えていくためにはどういった活動が望まれるでしょうか。
堀内 診断に関しては、少しずつではありますが、この10年間の活動によって進んできたと思います。ただ、医療従事者でHAEを実際に診たことがある人は依然としてすごく少ないので、そういう方々がよく知らないまま薬を使うのは非常にハードルが高いと思います。
加えて患者さんにとって、自分がどこの医療機関を受診したらいいのかが見えにくいという問題もあります。飛び込みで受診しても、診てくれない病院は多いので。患者さんが円滑に治療を受けられるよう裾野を広げていくことが必要だと思います。
この地域なら、この病院に行けば治療してもらえるといったようなことが、容易に検索できるようなネットワークがほしいです。そうすれば出張とか、お子さんであれば修学旅行とかにも、安心して行けるようになりますよね。
秀 もう一つ難しいのは、誰にどこまでの治療を、あるいは、どこまでの医療資源を投入すべきかという問題です。修学旅行に行けないというのは非常につらいので、ぜひ行けるよう、万全を尽くすべきだと思います。しかし、スキーに行きたいという場合はどうでしょうか。その患者さんがスキーに行くために、何人もの医療従事者の手を借りなければならず、人件費もかかります。
臨床現場は、みんなが努力しながら限られた医療資源を分かち合い、人々の健康をできるだけ維持するために、多くの人たちが力を尽くしています。そうした中で、HAEのことをよく知らない先生が、「こんな高い薬は使えないよ」と言うのは、自然な反応だと思うんです。だから、知らない人にはぜひHAEのことを知ってもらいたいと思います。でも、知っていたとしても、では目の前の患者さんにどこまでの治療をするかを適切に判断することは、やはり難しいと思います。
なぜなら、この病気は常に具合が悪いわけではなく、まったく無症状な期間も結構あるわけです。しかも一年365日の360日ぐらいは平気な人もいれば、ほぼ一年中症状が出ている人もいて、非常に幅が広い。だから一律には治療内容を決められない。ここをどうしたらいいのか、治療のガイドラインを確立させるには、HAEに取り組む医療従事者だけでなく、いろいろな立場の人が参画して、考えながらつくっていくことが必要だと思います。
堀内 病気によって症状の進行の仕方はさまざまです。たとえば、私の専門であるリウマチは、症状がどんどん悪化する病気なので、食い止めるためには高額でも生物学的製剤を投与しないわけにはいきません。さもないと症状がどんどん進んで後戻りできないのです。
でもHAEは違います。発作が治まってしまえば健康体に戻るので、高価な薬をどんどん使って、二度と発作が起きないよう治療しようとはなりにくいかもしれない。コンセンサスが得られていないのです。そこは難しいところです。
秀 国際的には、ガイドラインが改訂されるたびに、患者が健常者と変わらない生活を送れるように早く診断して治療すべきだという方向に進んでいます。だけど、日本における実臨床の場では、必ずしもそうはなっていません。やはり日本なりのコンセンサスが必要なのではないかと思います。
堀内 QALY*3はどうですか。医療技術をどれだけ使えば、患者さんの生存年数とQOL(生活の質)がどれくらい上がるかといった、費用対効果を経済的に評価する。そういう数値を算出して議論ができれば、説得力もあるのではないでしょうか。
秀 そこは、私も自問自答してきました。私なりの一応の結論は、HAEの治療は、自動車の開発におけるF1レースのようなものなのではないかということです。一人の患者さんに多くのお金や医療資源を投じて治療することで、より多くの人が恩恵を受けられるようなさまざまな技術や知見を引き出せる可能性があります。
医療従事者は、HAEのことを深く知り、さまざまな治療経験を積むことで、やがて無駄のない薬の使い方ができるようになるでしょう。その結果、大きな節約を実現させる可能性もあるわけです。これは、目の前にいる一人の患者さんだけでは計算できない影響力だと思います。やはり、そうした未来への創造性こそが、我々が取り組む意義だと思います。
堀内 希少疾患に対する薬はいろいろ出ていますが、いずれも非常に高額ですよね。でもそれが、ほかの疾患の治療にも広がって、たくさん使われるようになれば、薬価も下がり、より使いやすくなりますよね。リウマチの分野ではすでに、そういうことが起き始めています。
田尾 DISCOVERYは早期診断にフォーカスをしていますが、治療の段階でもさまざまな葛藤があることが理解できました。我々としては、DISCOVERYのような取り組みが世に認知されることによって、もっともっとHAEや希少疾患に光が当たってほしいと考えています。
その過程で、薬の費用対効果や医療資源の最適化についても、医療財政の観点のみならず、秀先生、堀内先生がお話くださったように希少疾患の特性や波及効果を加味した議論がなされるべきですね。そして、何よりも、いまもどこかで病気と戦っている患者さんを救うきっかけになればと強く思います。