杉田 私は人事とエシックス&コンプライアンス(倫理および法遵守)をグローバルに見ていますが、いまやどこの企業でもイノベーションを意識している時代です。その中で、これまでのような管理型のアプローチはフィットしなくなっていると感じます。コロナ禍をきっかけに進んだリモートワークもあり、フルリモートで働いている社員がふだん何をしているか、詳しく知ることはできません。型にはまった管理は物理的にも不可能であり、ジョブというくくりで人材を管理することは、急速に難しくなってきています。イノベーションを意識する企業では、成長に合わせてジョブも変化しますから、なおさらジョブで管理することは困難です。当社でいえば、研究開発に従事している社員には、ジョブでは測れないようなことをどんどんやってもらわないと困ります。そう考えると、測れるのはスキルだと思います。
その点、日本はジョブというより、みずからのスキルやエクスパティーズ(専門的な技術や知識)を磨き上げる意識のほうが合っていると思います。みずからのスキルの面積を拡大していくアプローチのほうが受け入れやすいのではないでしょうか。
ただ、業界によってスキルの見極めの難しさには差があると思います。IT業界は比較的容易な一方、当社の研究開発部門などは簡単ではありません。むしろ重要になってくるのは、ほかから見てどういう評価がなされているかというレピュテーションだと思います。
周辺の人間から頼られているか、必要な情報を持っているネットワークに属しているかといったことです。
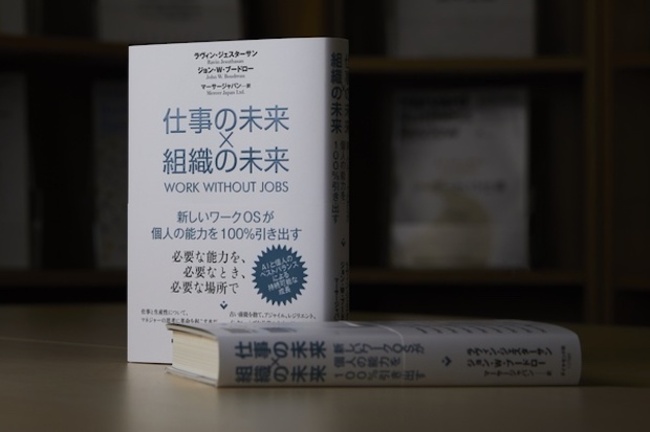
ラヴィン・ジェスターサン/ジョン・W・ブードロー=著
マーサージャパン=訳 ダイヤモンド社 定価2420円(税込)
白井 注目すべきネットワークに入っているということは、その領域で認知されている証明にもなりますね。医薬の世界では、所属している学会も評価の対象になりそうです。
杉田 当社に海外人材がジョインすることになった時、いま所属している学会から離れてもらうべきかどうかという議論がありましたが、私はそのままでいいと伝えました。これまでの考え方だと、既存の関係性を一度整理してもらって100%専念してほしい、と考えそうですが、能力を100%使って専念してくれなくても、10%の時間で120%の成果を出してくれればいいのです。
組織は開かれた構造へ
リーダーのスキルに変化
白井 会社組織や人材マネジメントの研究の場では、いまだに会社固有のスキルを持っていることが強みの源泉であり、流出させないほうがよいという論調がありますが、人材がオープンに出入りするような組織のあり方がベターであり、組織には、スキルをうまくコーディネートできるキーパーソンが必要です。そういう企業が勝ち筋を握っている気がします。

