2023年3月期連結業績は売上高が初めて10兆円を突破、営業利益も1兆3024億円(*)と過去最高を更新するなど、業績好調なソニーグループだが、新たなテクノロジーの登場によるビジネスモデルの破壊やマクロ経済の影響で、「特に2008年からの7年間は利益が落ち込み、厳しい経営環境でした」と、十時氏は振り返る。
*IFRS(国際会計基準)17号適用に伴う修正再表示後の営業利益
転機は平井一夫氏がCEOに就任した2012年。そこから「ソニー再生」の物語が始まった。その道のりを十時氏は、中期経営計画のフェーズに沿って説明した。
「ソニーの変革」がテーマの第1次中計(2012〜14年度)では、事業ポートフォリオの見直し、デジタルイメージングやゲームなどコア事業の強化、テレビ事業のターンアラウンド(事業再建)、新規事業の創出に重点的に取り組んだが、「社員のマインドセットやカルチャーを変えていくことを重視しました」(十時氏)。
続く第2次中計(2015〜17年度)では、「利益の創出と成長への投資」をテーマとした。一律に規模を追わず、収益性重視を徹底するために、各事業の位置付けを明確化。具体的には、成長牽引、安定収益、事業変動リスクコントロールの3つの事業領域を設定した。成長牽引領域には積極的に投資する一方、市場が成熟化している安定収益領域は、キャッシュフローの創出を強化。スマートフォンなど差異化が難しいプロダクトが多い事業変動リスクコントロール領域では、事業のスリム化を図った。
CEOが吉田憲一郎氏にバトンタッチされた第3次中計(2018〜20年度)では、「持続的な社会価値と高収益の創出」をテーマに、3つの点にフォーカスした。消費者と直接つながるDirect-to-Consumer(DTC)サービスとコンテンツIPの強化、高級ミラーレスカメラに象徴されるブランデッドハードウェア事業でのキャッシュフロー創出、そしてCMOSイメージセンサー領域のさらなる強化を図った。
こうした9年間にわたる再生計画の実行によって、2012年度に約1兆7000億円だったソニーの時価総額は、20年度に14兆円を超え、企業価値は8倍以上に高まった。
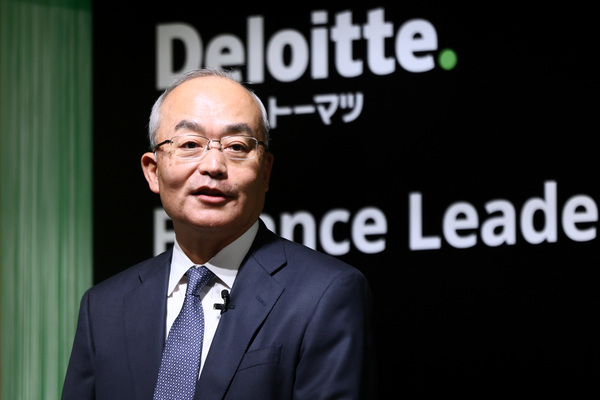
ソニーグループ
取締役 代表執行役 社長 COO 兼 CFO
「感動」をPurposeに昇華させ、そこに「成長」を加える
2023年度が最終年度となる第4次中計は、「ソニーの進化」をテーマに、「売上げと利益の両面でバランスの取れた成長を推進しています」(十時氏)。第4次中計のトピックとして、KPI(重要業績評価指標)を3年間累計の調整後EBITDA(利払・税引・償却前利益)に変更したことが挙げられる。
第1次から第3次の中計では、期間ごとに営業利益率や営業利益額、営業キャッシュフローなどをKPIとしてきたが、償却負担が大きい投資などにはどうしても慎重になってしまう。3年間累計の調整後EBITDAをKPIにしたのは、「各事業セグメントが、一定の規律の中で将来の成長に向けた投資を積極的に行うよう後押しする意味があります」。
2012年からの再生の過程において、平井氏が掲げた「感動」というキーワードを、吉田氏が「Purpose」(パーパス)へと昇華させ、ポートフォリオ経営を本格的に推進してきた。2024年度からの第5次中計では、そこに「“成長”という大きなテーマを加えていきたい」と十時氏は考えている。
成長への取り組み、投資家との積極的な対話へ
十時氏がCFOに就任した2018年から、ソニーではキャピタルアロケーションを公開し始めた。稼いだキャッシュをどういう優先順位で投資するかは、投資家にとって大きな関心事だからだ。
2018〜20年度累計のキャピタルアロケーションを見ると、営業キャッシュフロー(金融事業を除く)を中心とした2.8兆円を原資とし、CMOSイメージセンサーの生産能力増強など設備投資に1.2兆円、DTCサービス強化のためのコンテンツIPや音楽出版権の取得、自己株式の取得など戦略投資に1.4兆円、配当に2000億円という資金配分となっている。
こうしたキャピタルアロケーションの結果、事業ポートフォリオも大きく変わった。エンタテインメント事業が売上高に占める割合は2012年度の28%から2021年度には51%に高まり、営業利益ベースの構成比は同じ期間に38%から64%に拡大した。いまやエンタテインメントが、グループの中核事業となっているのである。
組織における多様性の進化が、さらなる価値創出に
ソニーではパーパス経営を推し進めている。吉田氏が中心となって新たに設定したPurpose(存在意義)は、「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。」。同時に「夢と好奇心」「多様性」「高潔さと誠実さ」「持続可能性」という4つのValues(価値観)も定めた。これらのPurpose&Valuesによって多様な事業と人材のベクトルを合わせ、創出価値を高めていこうとしている。
「一番苦しい時期を乗り越えられた要因を振り返ってみると、ソニーグループには多様な人材がいて、多様な事業があり、それらを組み合わせ、活かせたことが大きな学びであったと思います。その多様性をさらに進化、発展させ、価値創出と成長を加速させたいと思っています」。グレート・トランジション時代におけるソニーグループの成長と進化について総括し、十時氏は講演を締めくくった。