榊原 IBMでは、外部からやってきたルイス・ガースナー氏が1993年にCEOに就任して、ハードウェア事業からサービス事業への大転換を実現させました。当時の私はまだ若手のエンジニアでしたが、会社がダイナミックに変わっていくのを肌で感じました。
先ほど述べた通り、マイクロソフトでもクラウドシフトという大転換を経験しました。パナソニック コネクトもさまざまな変革が必要な会社なので、世界的なIT企業2社での変革の経験が活かせたらいいと思っています。
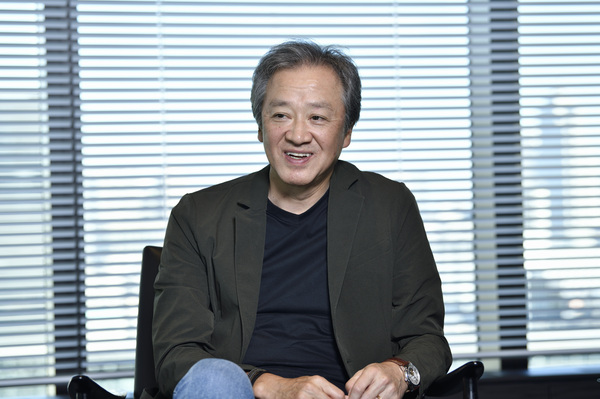
Akira Sakakibara
パナソニック コネクト
執行役員 ヴァイス・プレジデント
チーフ・テクノロジー・オフィサー
ソフトだけでなく、ハードがあるからわくわくする
森 パナソニック コネクトにおけるCTOとしての役割と、榊原さんが率いている技術研究開発本部のミッションについて教えてください。
榊原 パナソニック コネクトはパナソニック ホールディングスの傘下にある事業会社の一つで、2022年4月に発足しました。事業としてはB2Bに専念していて、ハードウェアとソフトウェアの両方を持っています。
ハードウェアは、半導体実装装置のような回路形成機器と、アーク溶接やレーザー溶接ロボットなど熱加工機器を製造・販売するプロセスオートメーション事業、放送用業務機器や高度なプロジェクションマッピングなどに用いるプロジェクターなどを手がけるメディアエンタテインメント事業、ノートPCやラガダイズPC、決済端末などのモバイルシステム事業、乗客向け機内エンタテインメントや機内Wi-Fi接続などを手がけるアビオニクス(航空機向け電子機器設備)事業の4つがあります。
ハードウェア事業は、事業ポートフォリオの整備を進めて、それぞれの販売シェアが世界トップグループにいるか、利益率が高いものに絞っていますので、言わばキャッシュカウ的な事業です。ここで稼いだキャッシュを使って、成長分野であるソフトウェア事業を強化しています。代表的なものとして、SCM(サプライチェーンマネジメント)ソリューションの世界大手である米ブルーヨンダー、物流・人物認証とモビリティソリューションに強いベルギーのゼテス(Zetes)があります。いずれもM&A(合併・買収)で傘下に収めました。
森 ハードからソフトまで、CTOとして扱う技術が非常に幅広いですね。
榊原 たとえば、半導体実装装置では、ハンダが塗られた基板の上にチップを吸着したガイドがものすごいスピードで動きながら、1ミリの狂いもなく該当の箇所で止まってチップを装填しなくてはいけません。そういうハードウェアの性能は、ソフトウェアによる制御技術との組み合わせで決まります。
今後はリカーリングビジネスへシフトしていくつもりですが、そのためにはハードウェア技術も磨かなくてはなりません。目指しているのは、ソフトとハードの組み合わせにクラウドのコネクティビティをつけ足して、もっと高度なサービスを提供することです。社内ではそうした事業展開のステップアップを「レイヤーアップ」と言っています。いま、その仕掛けづくりをしているところです。
森 レイヤーアップしていくとなると、クラウドでのデータ処理とエッジでの処理とのバランスをどうするかといったアーキテクチャーや、アナリティクスの知識、技術も必要ですね。

Masaya Mori
デロイト トーマツ グループ
パートナー
Deloitte AI Institute 所長
榊原 私たちはCPS(サイバーフィジカルシステム)ループと呼んでいるのですが、生産ラインですとかロボットなどのデバイス、人の動作や空間使用の状況など、現場のあらゆる場所・モノから吸い上げたデータをAIで解析し、得られた洞察をデバイスにフィードバックする。同時に、クラウドではブルーヨンダーが生産計画や物流計画をつくって、コントロールする。その仕組みづくりをやっています。
地上戦(エッジコンピューティングやIoT技術)と空中戦(クラウド)を組み合わせたCPSループで、自律的に生産・物流計画を変更したり、制御したりできる「オートノマス(自律的)サプライチェーン」を目指して、ソフトウェア、AI、ロボティクスなどいろいろな技術をブラッシュアップしている最中です。
森 データでサプライチェーンを可視化して、分析・検知・予測し、自律的に最適化することを目指しているということですね。
榊原 その通りです。システムの自律性を高めたいと思っています。
森 ハードウェアや現場といった物理的なものづくりの世界が入ってくると、わくわくしますね。
榊原 そうなんです。私はIT業界が長く、しかもソフトウェアを開発することを主な仕事としてきまして、物理的なデバイスをみずからつくるといったことはあまりやってこなかったので、実験室に行くとわくわくします。

