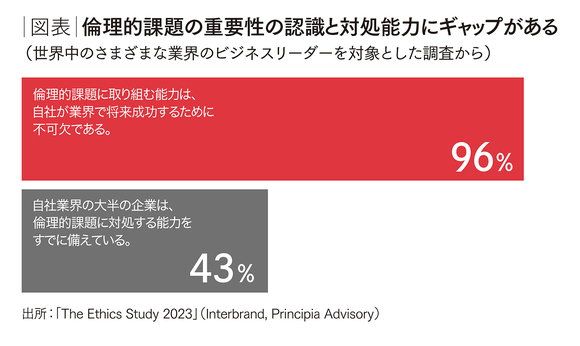-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
企業やビジネスリーダーの倫理が問われる局面が増えている。さまざまな社会課題に向き合いながら、組織として正道を歩み、ブランドや企業価値を高めるためにどう行動すべきなのか。そのために、組織倫理と企業文化をどうマネジメントしていくか。名和高司氏と並木将仁氏の対談を通じて、正解のない課題に直面するビジネスリーダーに深い示唆を提供する。
正解のない倫理的課題にポジティブに向き合う
並木 企業を取り巻く倫理的課題が複雑化しています。私は、組織倫理については大きく2つの論点があると思っていまして、一つは社会的にも経営的にも明らかにやってはいけないこと。たとえば、ハラスメントや不正です。
もう一つは、ステークホルダーの立場によって何が正しいかが揺れるテーマです。代表的なものとしては地政学的な衝突やテクノロジーの問題が挙げられます。前者のハラスメントや不正などは倫理的に何が正しいかは明確ですが、後者は正解がありません。
たとえば、AI(人工知能)やバイオテクノロジーの進化をどこまで受け入れ、どう活用するかは人や組織によって立場が異なりますが、そうした中で企業はスタンスを明確にすることを求められており、それがブランドの世界観や企業価値に大きく影響します。
後者に類するテーマが増えているため、企業としては倫理的課題への対処の難しさが増しています。
名和 少し視点をずらしてとらえると、倫理的課題にはネガティブかポジティブかという二面性があります。不祥事などネガティブなことをやってしまうとブランド価値が損なわれるのは間違いありません。これはカント的な思想に基づく、義務や正義を重視する倫理観と言ってもいいかもしれません。
一方で、正解がない倫理的課題については、ポジティブに新しい価値をつくっていくことが求められていると私は思います。アリストテレスは、人が幸福になるために「より善く生きる」ことを倫理ととらえていました。現代風に言うと、ウェルビーイングの追求です。
ウェルビーイングな状態は人によって異なるので、とらえどころが難しいのですが、何が正しいのかが揺れ動く世の中で、“青い鳥”を追い求めたいという気持ちはますます高まっています。みずからの信念に基づきながら、人々が共感できる青い鳥を提示できたブランドの価値は高まっていくのではないでしょうか。
並木 倫理という言葉を聞くとコンプライアンス的な狭い意味を連想する人が多いのではないかと思いますが、本来は哲学の一分野であるという大きな枠組みでとらえないと本質を見誤るリスクがあります。
(民泊仲介大手)米エアビーアンドビー(Airbnb)で最高法務責任者と最高倫理責任者を務めたロバート・チェスナット氏に『インテンショナル・インテグリティ』(Intentional Integrity)という著書があります。これは、リーダーがインテグリティ(誠実さ、高潔さ、統合性)のある組織文化を醸成し、組織倫理を実践するためのステップについてみずからの経験に基づいてまとめた本です。
私は彼に会った際に、「どうして著書のタイトルにエシックス(倫理)という言葉を使わなかったのですか」と尋ねました。それに対して彼は、「エシックスという言葉は狭く解釈されやすい。リーダーが醸成すべき組織文化を表すには、インテグリティがふさわしいと考えた」と答えました。
私はそれを聞いた時、たしかにインテグリティのほうが哲学的な広がりがあるし、名和先生がおっしゃった倫理が持つポジティブな側面を包含していると思いました。
名和 倫理的課題は両面とも重要なのですが、ポジティブな側面は見逃されがちですよね。