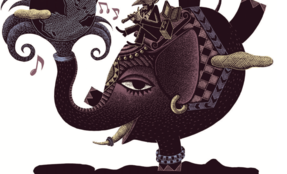-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
中国産業界の弱点:マネジメント人材の絶対的不足
2006年現在、中国における1949年以前の資本主義体制を知る中国人経営者はほとんどいない。しかもその大半は、80年代から90年代、つまり社会主義体制下での市場経済政策が推し進められた時代に育ったとはいえ、具体的な経営モデルも、変化の時代にふさわしいツールも知らないまま、とにかくマネジメント・スキルらしきものを身につけた。
激動の中国現代史、たとえば大躍進政策[注1]、文化大革命、そして79年に鄧小平(トウ・ショウヘイ)が始めた「改革・開放」が解き放った不確実性の数々に翻弄され、その結果、現代中国はグローバル化しつつある経済を率いるだけの力を備えた人材に乏しい。いままさに資本主義への転換期にありながら、中国企業は、戦略、営業やマーケティング、財務/会計、人材マネジメントなど、さまざまな面で知識やスキルに欠けている。
こうした実務能力に加え、労働者とコミュニケーションし、交渉し、能力開発するスキルも強く求められている。しかし、そのような能力に優れた人材が決定的に不足しているため、ほとんどの中国企業がみずからの力で急成長する経済の波に乗り、その恩恵に浴することがなかなかできない。
ならば、先進国のビジネススクールに幹部社員を派遣すればよさそうなものだが、一定水準以上の教育を受けたマネジャーさえ少なく、ましてビジネス教育となると、推して知るべしである。ここに英語が話せないことも加わって、とても留学など不可能である。若年層でも、事情はほぼ同じである。中国の起業家にはさまざまなチャンスが広がっているとはいえ、大半は己の機知と決断力以外に頼るものがない。
そこで中国では、中国語で学べるMBAやEMBA(エグゼクティブMBA)へのニーズが急速に高まっている。ところが、この分野でのベテラン教員が不足しているため、結局先進諸国から招かざるをえない。2006年、中国の一流大学はこぞってMBA教育を提供しているが、その名称を見る限り、スクール・オブ・エコノミクス、ビジネススクール・オブ・インターナショナル・ビジネス、MBA教育センターなど、かつての計画経済の残滓(ざんし)を感じてしまう。
マネジメント・スキルへのニーズの高まりと国内におけるマネジメント教育の場の絶対的不足を考え合わせれば、この国で教育機関を発展させ、革新する必要性は言うまでもない。
90年代初頭、中国国務院教育部はMBA教育に乗り出した。いまなお黎明期にあるとはいえ、マネジメント教育は過去15年の急速な経済発展への貢献を認められている。卒業生は実社会で実力を発揮し、北京大学、復旦(フダン)大学、清華大学などの一流大学のビジネススクールでは、おしなべて質が向上しているという。
91年以来、中国のビジネススクールは、世界の水準に追いつき、自国企業のニーズを満たすために、長足の進歩を遂げてきたことは疑いようがない。しかし2006年現在、他国とは異なる独自のビジョンを構築しなければならないこと、そのためには継続的かつ協調的な努力が不可欠であることも間違いない。
実際、中国のビジネススクールの多くは、中国政府の戦略を考慮すれば、これまでハーバード大学をはじめ、大半のビジネススクールが開拓してきた道ではなく(囲み「アメリカのビジネススクール小史」を参照)、中国の将来につながる「第3の道」、すなわち独自のマネジメント教育を試行錯誤すべきであると認識している。