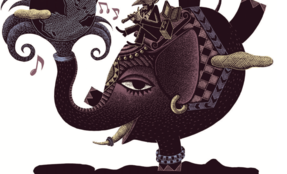-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
「未来の霧」に包まれた
新興市場の攻め方
安定した業界や先進国で事業を学び、成功を収めたビジネス・リーダーが、不安定な市場ではつまずいてしまうことがある。その理由の一端は、未来は遠くまで見通せるものであり、長期的な戦略がしっかりしていれば、競争優位を守り続けられると過信していることにある。
乱気流が渦巻く市場環境では、不確定要因があまりに多いため、未来を読もうと目を向けても、視界は非常に暗い。ある要因が変化しても、他の要因が安定していれば、不確実性をコントロールできるかもしれないが、現実はそう甘くない。たいてい、大半の要因が不安定であり、しかも絡み合って予想外の結果をもたらす。私はこの不透明性を「未来の霧」と呼んでいる。
まず実例として、ヨーロッパの某通信会社の経営陣が「携帯電話の3G(第3世代)技術は業界に革命を起こす」と言っていたことを思い出していただきたい。彼らはこの判断に従って、各種技術のライセンスを取得するために1000億ドルを投じた。しかし現在、3G技術は急進的な革命ではなく、むしろ漸進的な進歩であるらしいことがわかってきた。一般への普及度も、技術の進歩も、経済効果の拡大も、予想を下回っているのが実情である。
この新技術は通信会社にどれほどの価値をもたらすのか。これは、相互に関連し合う、さまざまな要因、たとえば投資効率を左右する規制当局の方針、代替技術の進歩、投資家たちの後発技術への関心度、消費者が抱く携帯電話への期待などの影響を被る。したがって、市場環境が長期的にどのように変化していくのかなど、ほとんど予想不可能といえる。むろん、3G技術への莫大な投資をまったく回収できないと申し上げているわけではない。できるかもしれないし、できないかもしれない。
別の例で言えば、我々の目の黒いうちに、中国はアメリカを凌ぐ超大国になるかもしれないし、1990年代のドットコム企業や、80年代の日本企業がそうであったように、欧米諸国の企業経営者たちに数年間の恐怖を与えただけにすぎないかもしれない。また、ゲノム創薬の登場によって、医療費の大幅削減がもたらされるかもしれないし、そうならないかもしれない。
乱気流が渦巻く市場とは、そういうものだ。何らかの変化が起こるか否か、その変化が他の要因とどのように影響し合うのか、とにかく起こってみない限り、わからないのだ。
予測がつかない市場での経営行動に関する研究というと、その大半は、80年から2005年までのアメリカIT産業に関するものである。しかし本稿では、その対象をより広げて、さまざまな国、時代、業界における不確実性について取り上げる。
私はこの6年間、世界で最も変動の激しい市場で事業展開している企業──対象国は中国とブラジル、業種は業務用ソフトウエア、通信、航空機など──を調査するプロジェクトを指揮してきた。
本プロジェクトでは原則、不確実性をうまく乗り切ってきた一社とあまりうまくいかなかった同業他社一社について20組以上を比較している。その比較結果と成功の共通点を分析することで、予見しにくい市場で生き残り、みごと成功を収める経営原則をいくつか抽出することに成功した。