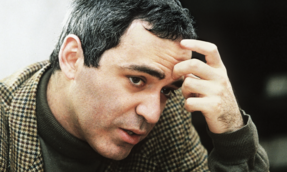-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
アナロジーは戦略思考の王道である
戦略とは選択である。すなわち、戦略の本質は、何を実行し、何を実行しないのかを選択することにほかならない。このような選択にまつわる思考の質こそ、優れた戦略を立案し、企業を成功に導くカギとなる。
戦略家は、戦略の意義や数字、あるいはアクション・プランなど、具体的な内容を詰めることばかりに気を取られ、己の思考法について一歩離れて省みることはまずない。しかし、己の推論プロセスを理解することはきわめて有意義である。とりわけ、戦略的意思決定において「アナロジーによる推論」が大きな役割を果たしているにもかかわらず、そのことが往々にして見過ごされがちである。
我々は未知なる問題やチャンスに直面した時、まず過去に経験した類似の状況を振り返ってみることが多い。そこから何らかの教訓を見つけ出し、目の前の状況に当てはめる。
ところが、このようにアナロジーで思考していることを自覚している人は皆無に近い。そのため、アナロジーの威力と落とし穴について、心理学者や認知科学者、あるいは政治学者がいくら洞察を積み上げても、ビジネスマンには無用の長物にすぎない。
アナロジーで思考している自分に目を向ければ、戦略上の意思決定の質を高め、判断ミスを減らすことができる。
我々はこれまで、さまざまな業界の戦略担当役員たちに、アナロジーの概念について説明してきた(囲み「本研究の背景について」を参照)。その際、ほぼ全員が過去の自分がアナロジーに依存していた経験を思い出した。アナロジーを用いて推論することがいかに一般的か、有名な例をいくつか挙げてみよう。
本研究の背景について
アナロジーを用いた推論について、我々の関心を駆り立てたのはフィールド調査である。
ポータル・サイト業界における戦略の起源を探し求めている際、こんなにもアナロジーが広く頻繁に利用されているさまに驚かされた。
その後、マネジャーたちや研究者仲間との議論、一人になっての沈思黙考を繰り返しながら、アナロジーによる推論が、戦略の立案に重要な可能性を秘めていることを認識するに至ったのである。
この認識に促されて、さまざまな取り組みを進めた。その一環として、心理学、認知科学、政治学、言語学におけるアナロジー関連文献を調査し、また、ビジネススクールの授業のなかで、アナロジーによる推論の使用法に関する調査や改善策を実施した。
ペンシルバニア大学ウォートン・スクールのダニエル・レビンソールと共同で、コンピュータ上でモデル化した「経営者たち」が、アナロジーによる推論を用いて戦略上の課題を解決するシミュレーション・ソフトを開発した。
今回の調査できわめて重要な要素は、おそらく我々2人の経歴がまったく異なることだろう。一人は人間の推論の限界を重視する、ウォートン流の行動科学アプローチに基づく経営学のなかで育ってきた。もう一人は、合理的な経済的選択の威力を重視する、ハーバードの伝統的な戦略思考のなかで育ってきた。
アナロジーによる推論は、我々2人の中間に位置づけられるものである。それは人間の認知能力を限界まで活用する、きわめて強力な推論方法といえるだろう。
インテル
1990年代半ば、インテルは、普及型PC向け低価格マイクロプロセッサーの発売をずっと差し控えていた。97年、ハーバード・ビジネススクール教授のクレイトン・クリステンセンが同社の経営者研修で、次のような鉄鋼業界の教訓を説明した。