則末 コミュニケーションにおいては、ITやデジタルに関する最新情報を適切に共有することに加え、普段からカジュアルに会話できる関係を築くことを大切にしています。これは経営トップに限りませんが、肩肘張らない会話の中から人間関係は深まっていきますし、お互いの人間性をわかり合えれば本音の議論ができると考えています。
桑野 IT・デジタル部門は、経営層や事業部門に対して受け身の姿勢になりがちですが、価値創造に向けた前向きな提案をしていくためにも、普段からのコミュニケーションや人間関係の構築が重要だということが、則末さんの話を伺うとよくわかります。
組織再編によって生まれたABDi内部での共創カルチャーの醸成という点で、工夫していることはありますか。
則末 私は「善循環」を意識しています。オートバックスセブングループ全体を一つのバリューチェーンと捉えた時、新たなシステムを開発したり、既存のシステムを改善したりすることで、それを使っている社員の仕事が楽になり、お客様によりよいサービスを提供できる。あるいは、そこで培った技術をB2Bのソリューションに活かすことで、取引先企業に価値を実感していただける。そのようにして顧客価値が高まると、我々の企業価値も高まっていきます。
つまり、社員やお客様にとっての「善」が循環して、新たな価値が創造されていくわけで、その価値創造サイクルの中で一つひとつの部門や一人ひとりの社員が果たしている役割を説明し、それを理解してもらえれば、自然と共創カルチャーが育まれると思っています。

オートバックスセブン IT管掌
オートバックスデジタルイニシアチブ 代表取締役社長
データドリブン企業への変革プロジェクト
桑野 御社の「データマネジメントセンタープロジェクト」に私たちは2023年から参加させていただいていますが、このプロジェクトが始まった経緯をお聞かせください。
則末 データドリブンな会社に変革するために2019年に立ち上げたプロジェクトです。
当時は顧客データや車両データが事業間、部門間で共有されておらず、全社で統一された顧客コミュニケーション戦略が実行されていませんでした。そこで、グループ横断で有志を募ったところ、IT・デジタルに限らず、マーケティングや営業、商品部門、物流部門など、さまざまな組織からメンバーが集まりました。
まずは顧客データを全社的に共有するための基盤として、CDP(カスタマーデータプラットフォーム)の導入に着手し、2022年に構築が完了しました。
そして、データによる価値創出にマーケティング領域から着手し、需要予測やマーチャンダイジング(商品政策)などに段階的に広げていくロードマップを策定し、マーケティングオートメーション(MA)導入に関する提案を何社かに依頼したうえで、御社との契約に至ったという経緯です。
桑野 2023年にMA導入を開始して実装が完了し、現在は本格的な運用が始まっている段階ですが、2019年のキックオフからここまで、プロジェクトは非常に順調に進んでいるとお見受けします。何よりプロジェクトメンバーの方々が、ITやデジタルを非常にポジティブに捉え、組織を超えて連携している。これは、なかなか稀なケースだと思います。
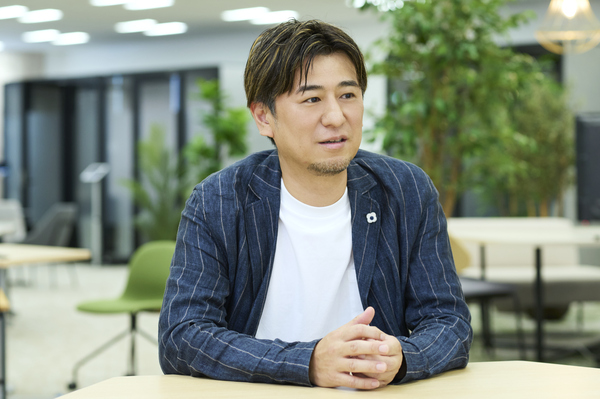
プレイド
執行役員 CGO(Chief Growth Officer)
則末 「この指止まれ」で公募したので、モチベーションの高いメンバーが集まっています。上司から言われて仕方なしに参加するのとはまったく違います。
桑野 公募とはいえ、これだけモチベーションの高いメンバーが集まったのはなぜですか。
則末 もともと、車が好きで、オートバックスも大好き、もっといい会社にしたいと思っている社員が大勢いるのです。
いまの時代ですから、データをうまく活用しないと我々のビジネスは進化していきませんし、お客様に価値あるサービスを提供することができない。それは、メンバー誰もが感じていたと思います。そんな時に、みずからチャレンジできるプロジェクトがあるのなら参加したいと考えたメンバーが集まったのではないかと思います。
社員が集まる場では、私も熱量を持ってプロジェクトの意義を語りましたし、いまでも本社のオフィス内にある「オートバックスデジタルラボ」で、勉強会やワークショップを開催しています。
桑野 それは社内研修制度の一環ですか。
則末 データマネジメントセンタープロジェクトの一環です。会社全体のデータリテラシーを高めることも、このプロジェクトのミッションの一つなのです。
オートバックスデジタルラボでは、社内外向けに最新のデジタル技術やAIを使ったソリューションを展示していますが、そこに社員を集めて、テクノロジーを使って何ができるかを楽しみながら体験してもらったり、チームごとにデータやテクノロジーを使って実現したいことを議論し、発表し合ったりしています。
ワークショップでの発表には順位をつけて、優勝したチームには社長の堀井や私が自腹でランチをご馳走することもあります。ランチを食べながら「ああしたい、こうしたい」といろいろな意見が出てきます。
桑野 そういう活動を続けていらっしゃることが、社員の高いモチベーションにつながっているのですね。
MAの運用が本格化してきた現段階で感じている課題は何かありますか。

