価値創出の仕組みを設計する「アーキテクト」たれ
白坂 私の専門は「アーキテクチャ」です。さまざまな活動を「目的」と、それを実現する「手段」、そして手段を使って目的を達成する「仕組み」に分けた時、この「仕組み」こそがアーキテクチャです。
たとえば、アナログな手段をデジタルに置き換えただけでは、目的が変わらない限り、生み出される価値は本質的に変わりません。しかし、新たな手段の登場によって、これまで達成できなかった新しい目的の設定が可能になり、それを実現する仕組みを構築できれば、生まれる価値は劇的に変わります。この一連の変革プロセスが「トランスフォーメーション」であり、その根幹となる仕組みをデザインする人材こそが、我々が育成を目指す「アーキテクト」なのです。
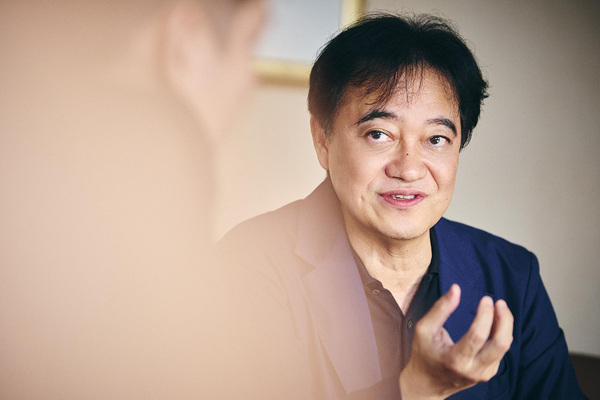
東京大学大学院修士課程修了(航空宇宙工学)、慶應義塾大学大学院後期博士課程修了(システムエンジニアリング学)。三菱電機にて宇宙開発に従事し、「こうのとり」などの開発に参画。技術・社会融合システムのイノベーション創出方法論などの研究に取り組む。2008年より慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント(SDM)研究科非常勤准教授。2010年同准教授、2017年同教授。2023年10月よりSDM研究科委員長。
農業用トラクターの自動運転を例に考えてみましょう。単に運転を自動化するだけでは、省力化にはなりますが、生み出される価値は変わりません。しかし技術が進化し、一人のオペレーターが複数のトラクターを遠隔操作できるようになればどうでしょうか。これまでとは次元の違う効率化が実現され、耕作放棄地の問題や食料安全保障といった、より大きな社会課題の解決という新たな目的が見えてきます。このように、技術(手段)の進化と、それによって設定可能になる新たな目的、そしてそれを実現する仕組みをワンセットで構想できるアーキテクト人材が、いまほど求められている時代はありません。
仁科 実は、スタジオゼロの中核を担う人材を「ビジネスアーキテクト」と呼んでおり、名刺にもそう記載しています。我々は目的や目標を設定することを「ピンを立てる」と表現するのですが、アーキテクトにとって最も重要なのは、まさに「どこにピンを立てるか」です。
白坂 おっしゃる通りです。現状の延長線上にピンを立てるだけでは、既存の仕組みの改善で終わってしまいます。しかし、まったく違う場所、あるいははるか遠くにピンを立てれば、そこに到達するための仕組みは既存のものとは大きく異なり、必然的に新しい手段や新しいチームが必要になる。その全体をオーケストレーションしながら新しい目的達成に導くのが、現代におけるアーキテクトの役割です。
仁科 私たちが日々向き合っているのは、経営者が長年解決できなかった根深い課題ばかりです。私たちはそうした課題に対し、どこから手をつけるべきかという「問いの出発点」を見極め、クライアントと一緒にリスクを取ってリーダーシップを発揮し、周囲を巻き込みながら実行までやり抜きます。課題の核心を見つけ、仕組みを構想し、実装する。白坂先生が定義されたアーキテクトの姿に重なります。

プレイド STUDIO ZERO 代表。NTTドコモ、セールスフォース・ジャパンで営業職やカスタマーサクセスを経験後、2017年CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」を提供するプレイドに参画。営業組織をリードしつつ、早稲田大学大学院経営管理研究科(MBA)修了。PR TableにてCFO/CPO(チーフプロダクトオフィサー)として企業経営に従事したのち、2021年4月プレイドに復帰。企業・組織の新規事業創出や既存事業の変革を支援する社内起業組織「STUDIO ZERO」を立ち上げ、代表に就任。
複雑な時代を乗りこなす「システム思考」の作法
白坂 現代の難しさは、環境が常に変化し続けることです。一度設計した仕組みが、すぐに陳腐化してしまう。だからこそ、設計した内容を状況に応じて修正できるメカニズム、つまり「変化に対応する仕組み」をあらかじめ組み込んでおく必要があります。
この「変化への対応」を考えるうえで、「DEOS」(デオス*)という工学的なアプローチがあります。これは「オープンシステムのためのディペンダビリティ(総合信頼性)工学」と訳されますが、ここで言うオープンシステムとは、目的や環境が常に変化するような複合的なシステムを指します。DEOSは、このようなシステムにおいて総合信頼性を維持しながら運用するための技術体系です。
*Dependability Engineering for Open Systemの略
DEOSには「デオスサイクル」という概念があります。これは二重のループで構成され、内側のサイクルでは日々の運用を監視し、不具合があれば修正する。一方、外側のサイクルでは、外部環境の変化や新たなリスクを分析し、より上位の概念であるゴールやシステムデザインそのものを見直すのです。経済産業省と総務省が策定した「AI事業者ガイドライン」に示されている「アジャイルガバナンス」の基本モデルも、このデオスサイクルを応用したものです。
仁科 システム思考的なフレームワークですね。
白坂 その通りです。しかし、現代ではさらに複雑な状況が生まれつつあります。それが「システム・オブ・システムズ」、つまり、独立して運用されている複数のシステムが、後から連携して、より大きな目的を達成しようとする巨大で複雑なシステムです。
たとえば、自動運転車と病院のシステムが連携する未来を想像してみてください。診察予約の時間に合わせて車が自動で迎えに来てくれ、交通渋滞が発生すれば予約時間が自動で変更される。将来は、病院だけでなく他の施設や、さらには「空飛ぶクルマ」とも連携するかもしれない。このように、設計段階で将来のすべての連携パターンを予測することが困難なシステムでは、従来の二重ループでは対応しきれません。そこで、これら複数のシステムを統合的に再学習し、アーキテクチャ自体を更新していく「トリプルループ」の学習プロセスが必要になると考えられています。
仁科 そのお話は、私たちの実感とも重なります。産業変革や社会発展において大きなインパクトを目指すほど、関わるステークホルダーの数は増え、利害調整や共有価値を生み出す仕組みは指数関数的に複雑化します。それぞれが部分最適でつくり上げてきた既存の仕組みを、全体最適の視点で再統合する。まさに、システム思考に基づいたリーダーシップが問われていると感じます。

