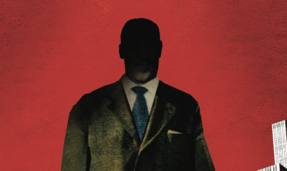-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
鬼上司への再評価
「気難しいリーダーは、いつからお払い箱にされてしまったのだろうか」。ウォルト・ディズニーのマイケル・アイズナー、ミラマックス・フィルムズのハーベイ・ワインスタイン、ヒューレット・パッカード(HP)のカーリー・フィオリーナなど、衝突を恐れぬ鬼上司が相次いで大企業のトップの座から滑り落ちていく事態に、テレビ・ニュース番組『ナイトライン』のキャスター、テッド・コッペルはこう問いかけた。
産業界でこのようなトレンドが芽生えかけていると察知した各ビジネス・メディアは、早々と鬼上司の時代の終焉を宣言した。『ウォール・ストリート・ジャーナル』紙は、これからは「厳格なリーダーが落ちこぼれる時代になる」と予想した。
「いや待て」と思われる向きもあろう。厳格なリーダーたちが「百害あって一利なし」ならば、なぜトップに上り詰めることができたのか。しかもけっして少数ではない。混乱を招くしか能がない人物ならば、甚大な損害を招く前に、出世コースから外れるか、クビになっていたはずではないか。
しかし、威圧的に支配するリーダーの多くは、かくも長きにわたって健在そのものだった。したがって、これらのリーダーたちに引導を渡す前に、情に流されぬやり方を、その短所のみならず長所も含めて、つぶさに分析してみる価値があるはずだ。そうすることで、効果的なリーダーシップの隠れた側面に光を当てられるかもしれない。
かつて硬直化や野放図状態、あるいは沈滞や放漫と形容されるような状態に陥った時、摩擦を恐れぬリーダーの力で改革を推し進めた結果、新たな方向に踏み出すことができたという企業や業界が存在する。そのような事例には、リーダーシップにまつわる何らかの示唆があるに違いない。
「モトローラの改革者」と呼ばれるエドワード・ザンダーの例を見てみよう。2004年1月、ザンダーがCEOに就任した当時、モトローラはとんでもない業績に陥っていた。それまでザンダーは生き馬の目を抜くようなシリコンバレーの世界に身を置いていたが、どういうめぐり合わせか、形式的で膠着した経営ゆえに「自動操縦」とまでいわれた企業の舵取りを任されたのである。
モトローラの立て直しという難しい仕事を引き受けるに当たり、ザンダーは「人に打たれるくらいなら、みずからをむち打て」という指針を掲げた。その時のモトローラを、彼は「血流が悪くて、動脈が詰まりかけている企業」と考えていた。
モトローラの場合、諸悪の根源はバイス・プレジデント層にあるというのがザンダーの判断だった。あるインタビューのなかで、彼は次のように語っている。「当社を去ったバイス・プレジデントは数え切れません。みずから身を引いた者もいれば、そうでない者もいます」
モトローラの改革は、まだ緒についたばかりである。それでもスタートは順調そのものだ。2004年度第3四半期の売上高は、86億2000万ドル(前年同期比26%増)と発表された。携帯電話の出荷数も、前年から15%増加した(2006年第1四半期においても、前年同期比23%増の100億ドル超の売上げを達成している)。