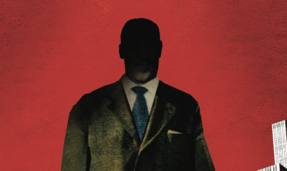-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
優れたリーダーを真似ても無意味である
リーダーシップを発揮するには、「本当の自分」を表現する必要がある。ジャック・ウェルチを気取ろうが、リチャード・ブランソンやマイケル・デルを真似ようが、だれかの模倣ではだめだ。自分とかけ離れたリーダーを演じてみたところで、部下からそっぽを向かれるのがおちである。彼ら彼女らが求めているのはリアリティなのだ。
これは、ある意味、現代における無秩序さへの反動でもある。また、政治家や実業家への幻滅が世間に蔓延しているからともいえる。したがって、だれしもが「騙されているのではないか」という疑いを心の内に抱いている。
うわべだけを取り繕うような、まがいもののリーダーシップへの不満が募っているからこそ、今日の企業で、本当の自分を表現する人材が求められているのだ。しかしそのような人材は、残念ながら不足している。
リーダーも部下も、本物志向と聞いて連想するのは、誠実さであり、正直さであり、高潔さである。本当の自分に裏づけられていること、これこそ優れたリーダーを見分ける要件なのだ。
ところが、本当の自分を表現できるリーダーシップに欠かせないというのに、そもそもリーダーたちが、本物志向という概念を誤解している例が少なくない。本物のリーダーであることを先天的な資質と考え、「人間はそもそも本物か、本物ではないかのいずれかだ」と思い込んでいるリーダーがまことに多い。
実のところ、本物かどうかはあくまで他者が判断すべき特性である。鏡をのぞき込み、「自分は本物である」といえるリーダーなど一人もいない。一人よがりの本物などありえないのだ。自分が本物のリーダーかどうかは、他者に与える印象によっておおむね決まる。そうであればこそ、自分らしさや信頼性を自己管理できる余地もまた大きい。
もし、本物であることが、完全に天性のものだとすれば、それを自己管理する余地も、ひいてはリーダーとして成長するための努力の余地もないということだ。さらに言えば、本当の自分を表現することに無頓着なマネジャーは、リーダーという役割を担ったとたん、窮地に陥るはめになる。
ピッツバーグの大手電力会社に勤務する、ビルという名のマネジャーの例を見てみたい。
もともと、ビルは電気工見習いとして入社したが、ほどなくその才能を見出された。大学に通うように人事部に勧められた彼は、そこそこの成績でその大学を卒業した。卒業後、彼は同じ会社に再び暖かく迎え入れられる。以来、プロジェクトを数多く手がけながら、自身のチーム・マネジメントのスキルに磨きをかけていった。