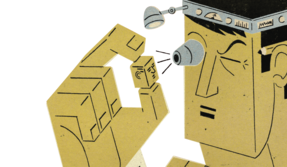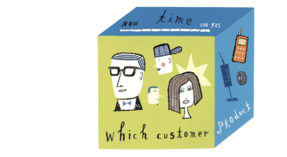-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
多機能を追求するか
使い勝手を優先するか
マウスパッドは、大判のコースターみたいでもある。主たる機能は、マウスを動かしても机の表面を傷つけないことであり、それ以外には、表面のデザインがユーザーを楽しませたり、疲れを癒したり、あるいはせいぜい宣伝になるくらいだろう。
ところが、「マウスパッド兼時計兼電卓兼FMラジオ」なるものが登場した。先頃、筆者の一人がこれを使うことになった。イヤホンつきというのは画期的ではあるが、電池が2つ必要なのに入っておらず、がっかりさせられたという。
2ページの使用説明書が添えられており、すべての機能を使いこなすには、少々時間を要することが察せられる。しばらくして、この新しいマウスパッドが机のいちばん下の引き出しに仕舞い込まれてしまったのは、言うまでもない。
同じようなことが、いまや世界中の家庭や職場で起こっている。さまざまな消費財が、たとえば携帯電話、ゲーム、電卓、ボイス・メール、無線LAN装置、PDA(携帯情報端末)、デジタルカメラ、MP3プレーヤー、GPS(グローバル・ポジショニング・システム)など、「これでもか」と言うくらいに、さまざまな機能を備えている。
〈BMW745〉には、ダッシュボードだけでも700以上の機能がある。韓国のLG電子はテレビつき冷蔵庫を販売している。ある販売店のホームページでは、「なぜLGの冷蔵庫にテレビがついているのか。つけない理由がどこにあろうか」と、わかったようなわからないようなコピーで、そのバリュー・プロポジション(提供価値)を宣伝している。
ソフトウエア業界では、こうした現象を「機能過多」(feature bloat)、あるいは「機能病」(featuritis)、「不愉快な機能」(feature creep)といった具合で呼んでいる。製品の機能といえば、以前はせいぜい1つか2つだったが、競争激化の果てに増加の一途をたどり、まるでかつての軍拡競争の様相を呈している。
問題は、多機能製品の使い勝手が悪いことである。カメラつき携帯電話などは格好の例だろう。隣接市場の製品が互いの機能を取り込めば、使用方法はおのずとややこしくなり、ユーザーをうんざりさせる。
エスプレッソ・コーヒー・マシンの〈ボッシュ・ベンベヌートB30〉でつくれるのは、デミタス・コーヒーだけではない。デジタル画面には12種の飲み物のほか、省エネ・モードやタイマー、硬水か軟水かなどが次々に表示され、それらすべてを選択しなければならない。