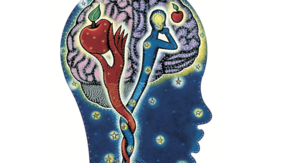-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
脳の働きを解明する
我々は、いつも万全な精神状態で意思決定を下しているわけではない。それゆえ、衝動的だったり、あるいは反対に慎重すぎたりして、判断を見誤ることがある。感情の赴くままにあっさり結論を出したかと思えば、次の瞬間には不安で身動きが取れなくなる。そうこうしているうちに、突如名案が浮かび、自分でも不思議に思う。
このような意思決定のメカニズムについて、我々は無知に等しい。しかし、人間の脳を調べる神経科学者たちが徐々に解明しつつある。その発見は、少々がっかりさせるものかもしれないが、必ずや役に立つことだろう。
研究が進み、人間の脳が動物のそれと大差ないことがわかってきた。我々の脳は、基本的にイヌのそれと変わらない。その違いは、人間の脳はイヌの脳と同じものの上に大脳新皮質が乗っていることである。おしなべて文明は、大脳新皮質という薄皮一枚によって築かれたのだ。
大脳新皮質は、計画や検討、決定などの行為を司るが、旧いイヌの脳の部分も休んでいるわけではない。新皮質とたえず連絡し合い、意思決定にプラスやマイナスの影響を与えている。ただし、我々はそれをまったく意識することはない。
脳の活動を調べるスキャニング機器を使えば、新旧の脳が協力、時には対立しながら、意思決定していることがわかる。だからといって、正しい意思決定を下したり、他人の意思決定をコントロールするための公式がすぐに編み出せるわけではない。
昨今「ニューロ・マーケティング」などと喧伝されているが、そう簡単なことではない。とはいえ、脳の意思決定メカニズムを理解すれば、自分をコントロールしやすくなるというメリットがある。
経済学の伝統的な実験のなかに、2人のプレーヤーが簡単な交渉をするゲーム、「最後通牒ゲーム」(ultimatum game)がある。この場合、各プレーヤーの頭のなかではどのようなことが起こっているのだろう。
このゲームは、金を所持しているプレーヤーが、そのうちのいくらかをもう一人のプレーヤーに渡すもので、所持金がたとえば10ドルならば、0~10ドルの範囲で渡す金額を自由に決められ、残りは自分のものにできる。ただしそれには、受け取る側が、その提示額に同意する必要がある。受け取る側は、提示額を聞いて断ることもできるが、断れば2人とも1セントも得られない。したがって、ゲーム理論の理屈で言えば、どんなにわずかな額であろうと、受け取る側は提案を飲むべきである。いくら少額でもゼロよりはましだからだ。
しかし、現実にはそうはならない。提示額が2ドルとか3ドルだと、受け取る側は決まって提案を断り、その報い──とはいえ、実際のところ何の報いだろうか──として金を失う。断った理由を聞くと、「相手のけちんぼぶりに腹が立ったから」と回答した。もちろん、当のけちな相手も、同様に金を失った。これでは理性の勝利とはいえない。被験者たちの言葉を聞くと、まるでイヌの脳が働いていた感じがするが、実はそのとおりなのだ。