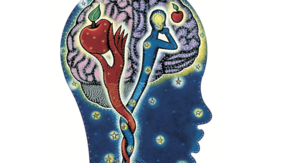-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
伝統的な戦略立案が意思決定の質を低下させる
「戦略立案ははたして無用の長物なのか」。最近、ある世界的なメーカーのCEOは、このように自問した。彼は2年前、自社の戦略立案プロセスの大々的な見直しを図った。それまでは、各事業部長が定期的に本社の経営委員会にプレゼンテーションするというものだったが、これはまったく機能していなかった。
経営委員会のメンバー、すなわちCEO、COO、CFO、CTO(最高技術責任者)や人事担当執行役員たちは、事業部門や職能部門のマネジャーによる果てしない〈パワーポイント〉プレゼンテーションに、ほとほとうんざりしていた。彼ら彼女らのプレゼンテーションを聞いていても、事業部門の仮説に異議を唱えたり、その仮説に影響を与えたりする機会はほとんどなかったからだ。
一方、事業部長たちにすれば、経営委員会の意見はお説教ばかりで、有益なアドバイスはほとんどなかった。そのうえ、このような戦略検討会議で優れた意思決定が下されることなど、望むべくもなかった。
そこで、このCEOが2年前に始めた改革では、戦略立案プロセスが最新のアプローチに変更された。
たとえば、各事業部門が提出できる戦略関連の資料は、きわめて重要なデータ15種だけに制限され、情報過多に陥ることを避けた。建設的な議論を促すために、プレゼンテーション・シートと補足資料はすべて1週間前までに経営委員会に提出することが義務づけられた。経営委員会のメンバーと事業部長たちが意見交換する時間を十分確保できるよう、戦略検討会議そのものの構成も変更された。
さらに、事業部長を本社に招聘する代わりに、経営委員会のメンバーが毎春、6週間をかけて、22の事業部門すべてを訪れ、会議に終日を費やし、事業戦略をもれなく検討することになった。まったく前代未聞のことだった。すべては、戦略の検討に費やす時間を増やし、より集中することで戦略検討会議の重要性を高めるためだった。
しかし、この新しい試みも失敗に終わった。CEOは、戦略立案の第2フェーズを終えた段階で匿名調査を実施し、新しいプロセスへのフィードバックを集めた。ところが、がっかりしたことに調査結果は苦情だらけだった。「時間がかかりすぎる」「要求水準が高すぎる」「現実の事業運営とかけ離れている」等々──。なかでもいちばんの打撃は、ほぼ全員が「新しい立案プロセスによって、何か決まった例しがない」と評価していたことだった。
CEOはあ然とした。最先端の戦略立案プロセスを導入したというのに、何も解決されないとはいったいどういうわけか。戦略を立案しながら、どうすれば、より多くの、より質の高い意思決定を、より素早く下すことができるのだろうか。
このCEOと同じく、多くの経営幹部は戦略立案プロセスの効果を疑い始めている。それも不思議ではない。我々の調査によると、戦略立案に費やす時間と労力にかかわらず、ほとんどの場合、戦略立案プロセスのせいで、優れた意思決定が阻まれている。そればかりか、戦略立案プロセスのほとんどが、戦略に現実的な影響力を持ちえぬまま、無為に繰り返されている。