データサイエンティストが
キャリアパスを描ける組織が必要
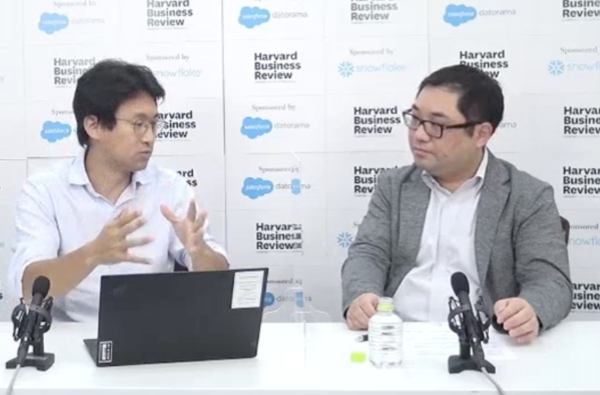
最後に、北川氏と渋谷氏がデータを活用する企業文化を作るということをテーマに対談した。渋谷氏がデータを活用する企業文化を作るには小さな成功を積み重ねることが重要だと繰り返したところ、北川氏は「やりやすいところから始めるのは良いと思うが、会社の文化になるほど大きく育てるには、どこかで『王道を歩く』フェイズに切り替える必要がある。王道とは会社内でも最も収益を上げている部署、柱となっている部署。一番動かしにくい部分だが、そこに入っていかければならない」と語った。
渋谷氏も、「そこを動かせれば一気に成長する」と同意し、そのためには社内のコミュニケーションを工夫する必要があるという。例えば「こっちのバナーの方がクリック率が1ポイント上がりました」と言うよりも、「年間に換算すると数千万円になります」という具合に、分析結果も生の数字を伝えるだけでなく金額に換算して伝えるようにすれば、経営層に届きやすいと語った。
さらに渋谷氏は、多くのデータサイエンティストが自身の仕事を、「数字としてアウトプットを出すこと」だけで終わらせてしまっていると指摘した。分析結果の生の数字を出すことが仕事であることは間違いないが、それだけでは経営層に全く響かない。金額で伝えるだけでなく、「これくらいの需要がある」とか「商売のチャンスがある」と、具体的に「もうかる話」をする必要があるということだ。
北川氏は「もうかるかもうからないかという話は結局、会社の経営課題のど真ん中から『逃げない』こと」だと表現した。さらに、「人間は自分の得意なことで攻めがちだが、データというものを会社組織の中核に持って行くには、会社の経営課題から逃げていてはいけない」と付け加えた。
ここで渋谷氏は「20代、30代で一生懸命データ分析をやって結果を出している人たちでも、ずっとこの先もそれだけやって仕事を続けていくだけなのか、データの専門家として経営陣に入っていくようなキャリアはないのか、といった不安を持っている」と、若手のデータサイエンティストが、キャリアパスが描けず不安になっている現状を指摘した。渋谷氏によると、今はデータサイエンティストが引く手あまたであり、企業が何もしないでいると、将来に不安を感じている人はいずれ辞めて他社に移ってしまうという。
そのような若手を処遇する方法として、渋谷氏は「ジョブ型採用」を提案する。データの専門家として高く評価し、キャリアパスも描いてみせて、高給で迎えるということだ。この点に気づいた一部の企業は、すでにジョブ型採用を始めているという。
さらに、渋谷・北川両氏は自身が務めているCDOという役職も、日本社会に浸透させていかなければならないと指摘。「そのためには、われわれが先鞭をつけて目指すべき姿を見せていかなければならない」と語った。