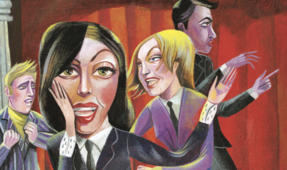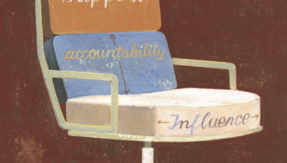-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
ヒューマン・シグマが業績を改善する
品質は、その評価や管理が簡単な場合もあれば、そうではない場合もある。たとえば、新しい携帯端末の製造工程について判断すべきことはもれなく把握されていることだろう。では、その携帯端末を売る小売店の販売方法についてはどうだろう。あるいは、その端末のややこしい使い方を消費者にわかるように説明しようと努めるコール・センターの担当者の対応についてはどうだろうか。
大半の企業がこのようなプロセスの質を評価し、管理することをあまり得意としていない。非製造部門の業務などについては同じことがいえるだろう。
しかし、いかなる業務も、その評価と管理について学習されなければならない。
製造部門では、価値が創造されるのは工場の作業現場である。一方、販売やサービス、とりわけ専門的なサービスの場合、価値が生まれるのは従業員が顧客とやり取りする場面である。このように、営業部門やサービス部門にすれば、従業員と顧客が接触する場が、言わば作業現場なのだ。これらの組織において、その業務内容や財務業績を大幅に改善するには、顧客接点を入念に管理しなければならない。
シックス・シグマなどの品質改善手法は、製造分野ではきわめて効果的といえる。というのも、製造分野での作業の中心は、予測可能性の高い要素を同じ方法で繰り返し組み合わせることだからである。しかし、人間同士が接する場ではいつ何が起こるかわからない。顧客接点では、このような手法はそれほど有効ではないのだ。
このシックス・シグマの限界に対応するために、我々は「ヒューマン・シグマ」と称する品質改善アプローチを開発した。シックス・シグマ同様、ヒューマン・シグマもバラツキの減少とパフォーマンスの改善が主要な課題となる。
ただし、シックス・シグマはプロセスとシステム、アウトプットの質に用いられるが、我々のアプローチは顧客接点に焦点を当てており、両者を評価する一貫性のある手法と、管理・改善につながる実行プロセスを統合させたものである。
ヒューマン・シグマの構想を練る段階で、我々は顧客と従業員とのインタラクションを評価し、これを管理する基本原則を発見した。それらは以下のようなものである。
・従業員と顧客のインタラクションを評価するに当たっては、経済学者やエンジニアのように思考しないことが重要である。合理性よりも感情のほうが双方の判断と行動に強く訴えるからだ。