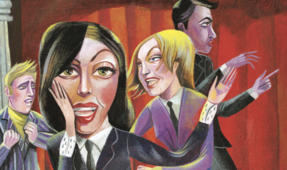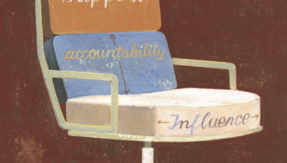-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
戦略と実績が乖離していく理由
3年前、ある大手メーカーの経営陣は数カ月かけて、ヨーロッパ市場の事業戦略を策定した。この市場には5年間で6社の競合企業が参入し、低コストの最新技術が発展する一方、市場シェアを獲得しようと激しい価格競争が展開されていた。ヨーロッパ事業はかつて事業ポートフォリオで重要なポジションを占めていたが、その業績は転落の一途をたどりつつあり、売却の是非についても検討が始められた。
ヨーロッパ事業の責任者は、業績を好転させるには斬新な問題解決手法が必要であると主張した。具体的には、事業基盤を生かし、販売後のアフター・マーケットやリース事業で成長を促すというものだ。この戦略によって、業績を急回復し、収益率と成長率で業界トップに返り咲けると考えたのである。経営陣もこの戦略に好意的で、必要な経営資源の投入を約束した。
ところが、3年が過ぎても、同事業の業績は目標値を大きく下回ったままだった。利益率がわずかに改善したとはいえ、資本コストは目標値にはほど遠かった。アフター・サービス部門と金融事業部門とも売上高と利益は目標値に達せず、コスト・ポジションも競合他社より劣っていた。
このメーカーは先頃、半日かけて戦略と業績を検討した。その会議の席上、ヨーロッパ事業の責任者は一貫して戦略の続行を主張した。「すべての戦略がいまだ実行中です。戦略自体は正しいものです。ただ、それが業績につながらないだけです。より熱心に、より賢明にこの戦略を続けるべきです」
しかし、CEOは迷っていた。業績低迷の原因は、戦略を実践できていないことではなく、戦略そのものにあるのではないか。ヨーロッパ事業の業績改善は最優先課題だが、責任者が訴えるように、このまま努力を傾けるべきなのか、それとも他の戦略を検討したほうがよいのか。実践方法に問題があるのなら、どうすれば改善できるのか。あるいは事業を売却して、損失を処理すべきなのか──CEOは釈然としないまま、結論を保留して会議を後にした。既存の戦略を続けたところで、業績が回復するのか、まったく自信がなかった。
たいていのCEOの方々が、これと似たような経験をお持ちのことだろう。多くの企業が膨大な時間とエネルギーをかけて戦略を立案するが、その努力が報われるだけの成果を実現している企業は少ない。我々の調査でも、戦略ならびに予想業績の達成度は平均63%にすぎない。
しかも、たいてい予想業績と実績が一致しない原因を正しく把握できていないため、間違ったレバーを引いてしまう。戦略の転換なくして業績は改善しえない状況にあって同じ戦略を続行したり、逆に全社一丸となって戦略を遂行すべき時に戦略を変更したりする。これでは、エネルギーと時間を浪費した挙げ句、業績は低迷していく。
ところが、我々の調査によれば、高業績企業は戦略と業績のギャップを見事に埋めていた。たとえば、バークレーズ・キャピタル、シスコシステムズ、ダウ・ケミカル、3M、ロシュなどである。これらの企業は市場動向を正確に把握し、現実的な計画を実行する。要するに、計画立案と実践のプロセスさえ整備できれば、実績が予想を下回るリスクを確実に低減させられるのである。
業績が予想を下回れば、すぐさま原因を特定して対策を講じる。そのプロセスは、独自の計画立案手法、全社的なプロセス管理による資源配分など、さまざまな手順を要する。我々の経験から言えば、これらが戦略の立案と業績の達成に抜群の効果を発揮する。