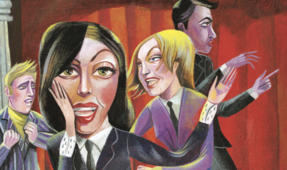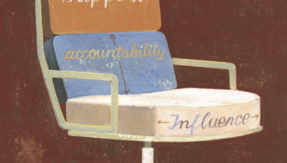-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
『エクセレント・カンパニー』の衝撃と意味
「だれがハイ・パフォーマーなのか」。マイケル J. シェル[注1]はこの問いに一家言ある人物だ。彼は、他の追随を許さない野球データの分析家であり、説得力あふれる論拠によって、史上最高の強打者を決定した。
野球の門外漢からすれば、史上最高のバッターを決める作業の難しさは言うまでもないが、それを証明することに400ページ以上も費やす──先頃著書Baseball's All-Time Best Sluggersがプリンストン大学出版局から出版された──必要があるのだろうかと首を傾げることだろう。
ヒットの本数を数えることがそれほど複雑とは思えない。しかし、シェルに言わせれば、数多の変数や注釈だらけのデータを組み伏せた作業であり、まがうかたなく、これは野球統計の聖杯なのだそうだ。しかし、世のなかには別の分析手法を用いて、彼に異議を唱える人も少なからずいるだろう。
産業界で最高のプレーヤーを選ぶこともまったく同様である。野球と違うのは、その作業がより難しいという点である。そもそもビジネスの観戦者には、拠りどころとするスコアボードさえない。勝者は、株式の時価総額が最も大きい企業なのか、それとも売上高成長率が最も高い企業なのか、あるいは単純に試合が終わるまで生き残っていた企業なのだろうか。もっとも、それも試合終了があればの話だ。
さらに言えば、各企業の置かれた環境を抜きに考えることはできない。不況時の高成長と好況時の高成長とでは、どちらがより優れているといえるのだろうか。最高の企業を決めるうえで何よりも難しいのは、ビジネス統計学の達人たちがみずから打ち立てた理論の根拠を示すことだ。つまり、最も偉大なのはだれかだけではなく、なぜそのように言えるのかである。
産業を横断し、時代を超え、各企業の業績を相対的に測定し、最高の企業を決定し、さらに成功要因の共通項を探り出すなどというのは気が遠くなる大仕事だ。やってみたところで徒労に終わる──そう思えるかもしれない。事実、ビジネスなるものが誕生してから1000年間、これを試みる者は現れなかった。
『ハーバード・ビジネス・レビュー』誌の目次を83年分振り返ってみても、当時マッキンゼー・アンド・カンパニーのコンサルタントだったトム・ピーターズとロバート・ウォーターマンが『エクセレント・カンパニー』を著す1980年頃まで、だれ一人として考えもしなかったことがわかる。だからこそ、彼らの著作が出版界に大旋風を巻き起こしたのだろう。
2人は経営コンサルタントとして、研究と実践の交差する場に身を置いていたが、彼らの『エクセレント・カンパニー』は、その双方に挑戦状を突きつけたのだった。経営者に対して、彼らの行動や態度次第で企業は勝者と敗者に分けられると述べる一方、研究者には、高業績を生み出す要因の特定は可能であると主張した。結局、その主張は正しかったのだろうか。その答えはおそらくノーだろう。
だれもが知っているとおり、彼らが「エクセレント」であると評価した企業のいくつかは、やがてそのリストから脱落していった。つまり、これら脱落企業にやがて訪れる困難を乗り切れるだけの資質が備わっていたかどうか、この著作が発表された当時にはわからなかったということだ。要するに『エクセレント・カンパニー』が与えた影響は、問題の解決ではなく、むしろ提起だったといえよう。