腹落ちしなければ
ビジョンは実現しない
――パーパス経営を自分事化してもらうために、味の素ではどのような取り組みを行っていますか。
西井 従業員エンゲージメント向上のためのマネジメントサイクルを回しています。私と各本部長との対話を起点に、組織・個人目標を設定し、個人目標発表会も行います。昨年は全42組織で実行しました。
次に、ベストプラクティスを社内SNSで共有し、1年に1回、社外有識者や社外取締役の皆さんが審査員を務める「ASV(Ajinomoto Group Shared Value)アワード」という形で表彰。さらにエンゲージメントサーベイを実施するという一連のサイクルを回していくものです。
なかでも、個人目標発表会は非常に効果的です。組織のトップがいる前で、新人からベテランまで全員がプレゼンテーションを行うのですが、自分がやっていることを他の人に聞いてもらうと同時に、他の人が何をやっているのか、組織全体としてどこに向かっているのかを理解することができるからです。
――西井社長は現在のパーパス経営に取り組む以前に、苦い経験があったそうですね。
西井 以前のビジョンは「確かなグローバル・スペシャリティ・カンパニー」というもので、マイルストーンとして「2020年にグローバル食品メーカーのトップ10入りを果たす」という目標を掲げていたのですが、2018年には目標に届かないことが見えてきました。
どうするのかと役員たちと議論をして、できあがったのが現在のビジョンです。幹部クラスと対話を始めた時に挙がったのが、「前のビジョンは腹落ちしなかったが、今度のビジョンは少なくとも腹落ちする」という声です。
新ビジョンの策定にあたっては、過去10年を役員たちとレビューしました。この間、何をやってきたのか、どう動いたのか、なぜ目標に届かなかったのか、責任の所在はどこにあるのかといったことを腹落ちするまで話し合い、共有しました。過去の経験を二度と繰り返さないように、新ビジョンについては絶対に達成するんだという思いで、従業員たちと対話を重ねています。
――パーパス経営が単なるお題目にならないようにするためには、何が必要ですか。
名和 パーパスはきれいごとで話しやすく、形はつくりやすいのですが、それを実現するにはエンジンが必要です。「バリュークリエイト(価値創造)」「バリューキャプチャー(価値獲得)」「バリューコミュニケート(価値伝達)」という3つの「VC」がそのエンジンになります。
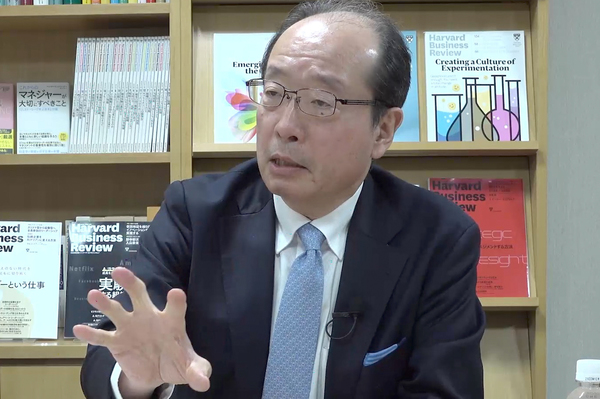
名和高司氏
バリュークリエイトは、顧客に対して新しい価値を生むこと、顧客と一緒に価値を共創することです。顧客に喜んでもらうのはいいけれど、新しい事業に投資をするための原資を確保しておかないと息切れしてしまうので、しっかりバリューキャプチャーしておく必要があります。そして、バリューコミュニケートは、自社の価値を高めていく活動をさまざまなステークホルダーに発信していくことです。これら3つのエンジンを装備せずに、口先だけで取り組んでもパーパス経営はうまくいきません。
もう1つは、パーパスやビジョンを社内に浸透させることです。西井社長がおっしゃった通り、味の素では2年かけて執行役員を説得し、現在は現場の従業員1人ひとりの共感を得るため対話を重ねているわけですが、そうしたプロセスが欠かせません。
――西井社長がパーパス経営を掲げられたタイミングは、ROIC(投下資本利益率)経営に注力していった時期と重なりますが、バリューキャプチャーのために投資効率を重視していったということですか。
西井 その通りです。売り上げで「グローバル食品メーカーのトップ10入り」を目指していた当時は、食品事業のポートフォリオを広げた結果、ROICが落ちてきて、バランスシートも悪化していました。このままでは、株主には還元ができても、投資家から次の成長のための資金を預けていただけないことに気がついて、収益に関するマネジメントポリシーを変更しました。
2020年度の実績でROICは6.9%ですが、2030年度で13%の達成を目標としています。2020~22年度は構造改革フェーズと位置づけ、非重点事業の縮小・撤退を完遂するとともに、業務効率化によるコストダウンを進め、2022年度に8%の水準を目指します。