なぜ名だたる有力企業が、弘前大学COI拠点に参画しているのか
波江野 健康データを集めることの重要性はわかっていても、実際に集めるのは簡単ではありません。弘前大学では住民と信頼関係を築く活動を長年にわたって続けてこられたからこそ、超多項目の健康ビッグデータを蓄積できたのだと理解しました。
その健康ビッグデータが基軸となって、弘前大学COI拠点でヘルスケアの研究と健康増進活動のオープンイノベーション・プラットフォームが形成されているわけですね。
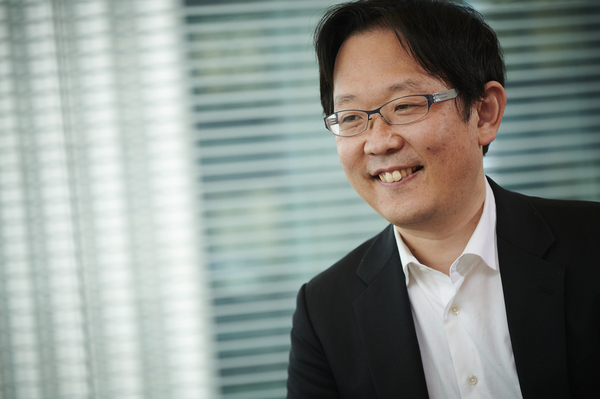
Takeshi Haeno
モニター デロイト
パートナー 執行役員
ヘルスケア ストラテジー
デロイト トーマツ コンサルティングにおける戦略領域のリーダー。モニター デロイトの中で、ヘルスケア戦略領域をリードしている。日本、米国、欧州デンマークそれぞれにおけるヘルスケアビジネスでの経験等をもとに、国内外の健康・医療問題について社会課題としての解決とビジネスとしての機会構築の双方を踏まえたコンサルティングを、政府、幅広い業界の民間企業などに幅広く提供。米カリフォルニア大学バークレー校 経営学修士・公衆衛生学修士。共著『未来を創るヘルスケアイノベーション戦略』(ファーストプレス、2022年)ほか、執筆・講演等多数。
村下 そうです。花王や味の素、サントリー食品インターナショナル、明治安田生命、ディー・エヌ・エー(DeNA)、資生堂など約50社の企業が参画しています。多数の共同研究に加えて、学内に16の共同研究講座(2022年10月現在)を開設し、超多項目健康ビッグデータをベースに課題解決に取り組んでいます。
「なぜこれだけの名だたる有力企業が、弘前大学COI拠点に参画しているのか」という質問をよく受けるのですが、第一には健康ビッグデータと最新科学で“健康長寿社会”を目指すという我々のビジョンが、広く企業の賛同を得られたことが挙げられます。
それに加えて、健常者の健康データを超多項目にわたって蓄積しているという独自性、優位性があります。たとえば、水分や野菜の摂取と健康の関係、食習慣と健康寿命の関係といった研究をしている企業が我々のCOIに参画していますが、企業単独でデータを集め、エビデンスを積み上げていくのは容易なことではありません。しかし、我々の健康ビッグデータを活用すれば、3000項目との関係性を見ることができます。
波江野 企業からすると、自分たちが解明したい研究開発課題と、3000項目の健康ビッグデータをひも付けられるのは、非常に魅力的だと思います。経営の意思決定、ないしは製品・サービス開発にも直接的に寄与する可能性があります。
一般的な健診項目だけでなく、個人の生活や社会環境に関するデータまで集めていらっしゃるのは、どういった狙いがあるのでしょうか。
村下 健康というのは、年齢や遺伝的な要因で語られることが多いのですが、実際はその人が置かれている社会環境、ふだんの生活習慣といった外部環境も大きく影響していると考えられています。
岩木ビッグデータは4層構造になっていて、分子生物学的データと生理・生化学データという2層の下に、個人生活活動データ、社会経済環境的データの2層があり、このすべてのデータがつながった3000項目になっているのが最大の特徴です。つまり、一つの項目と他の項目を関連付けた網羅的な解析ができるわけです。
心身ともに健康で、長生きしている人がふだんどういう生活をしているのか、どんなものを食べ、どのような運動をしているか、家族関係や社会との関わりはどうなっているのか。実はそういった点は、まだよくわかっていません。4層のデータを網羅的に解析することで、健康長寿とライフスタイルや社会経済環境の関連性を明らかにしていきたいと考えています。


