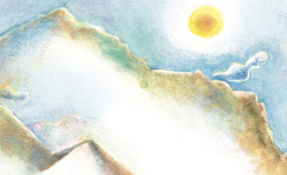-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
MBO幻想にはF. W. テイラーの影が見え隠れする
「目標管理」(以下MBO:management by objectives)というコンセプトは、もはやマネジメント・プロセスに欠かせなくなっている。にもかかわらず、マネジャーと部下の間に敵意や恨み、不信感を生み出し、これらがすっかり定着および強化されてしまっている。現在のようなやり方では、MBOとはいっても経営工学に新しい名前をつけて、より高いレベルの役職に適用したものにすぎなく、以前と同じ反発を買っている。
MBOの場合、明らかにそのコンセプトと実践との間に深刻な乖離がある。MBOの趣旨は業績評価であると同時に、フレデリック W. テイラー以来の伝統である、合理的なマネジメント・プロセスのさらなる追求を意味している。つまり、だれが何をやるか、プロセスを管理する実質的な権限はだれが有すべきか、報酬と個人の成果をどのように直接関連づけるかといったことだ。
MBOは本質的に、公正と合理性を高めるプロセスを踏みながら、より慎重に深く業績を予測・判断し、そして個々人が自分自身の目標を設定することで、自らを動機づけることを試みるものだろう。
職務上の義務を明確に規定し、社員自らが定めた目標を基準にその業績を評価しようという趣旨は筋の通ったものだ。部下の業績を正しく評価するために、上司と部下が同じ項目に留意するように配慮することは、実にまっとうなことである。部下が抱えている各業務について合意しておくことなど、まったくもって望ましい。
しかし、テイラー以来の伝統を受け継いだ合理化活動のほとんどと同様に、プロセスとしてのMBOは、マネジメントにおける最も大きな幻想の一つである。
なぜなら、モチベーションにおける、より深遠な感情的要素が適切に考慮されていないからだ。
現在ほとんどの組織で導入されているMBOが自滅的であり、単に個人にプレッシャーをかけることにしか役立っていない。本稿では、その理由を明らかにしたい。もっとも、だからといって即座にMBOも業績評価プロセスも否定するつもりはない。