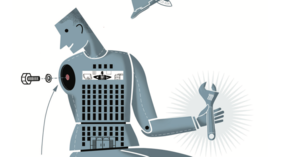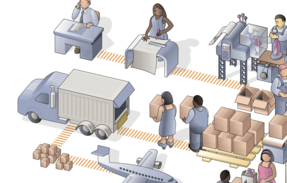-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
競合分析では見えない日本企業の強さ
昨今さまざまな業界で、新興グローバル企業の競争優位に何とか対抗しようと、欧米企業の経営者たちがやっきになっている。
人件費を抑制しようと海外に生産拠点を移し、グローバルに規模の経済を働かせるために製品ラインの合理化を推し進め、QC(品質管理)サークルやジャスト・イン・タイム生産を取り入れ、日本企業の人事慣行に倣おうとしている。それでもなお十分な競争力が得られないならば、他社との戦略的提携に乗り出す。その相手はほかでもない、自社の競争力を揺るがすライバル企業である。
これらの施策には、たしかにそれなりの意義があるが、たいていは模倣の域を出ない。ほとんどの企業は、途方もないエネルギーを費やした末、グローバル市場でライバルがすでに享受するのと同じコストや品質面での優位性を手にする程度である。
模倣は、相手企業を心から称える気持ちの表れかもしれないが、自社の競争力強化にはつながらないだろう。他社の戦略を模倣した場合、その戦略をすでに実践している企業からは、こちらの動きは手に取るように見えているはずだ。
そのうえ、成功企業の場合、現在に立ち止まることはまずない。このため当然ながら、多くの経営者がいつまでもライバルの後を追い続け、時折、相手の新たな成果に不意を突かれる。このような経営者と企業は、戦略の基本コンセプトの多くを問い直さない限り、かつての競争力を取り戻すことも、新たな競争力を獲得することもかなわないだろう[注1]。
「戦略」が注目を集めるのに従い、欧米企業はその活力を失っていった。我々2人は、これを偶然だとは考えていない。
たとえば、経営資源とビジネスチャンスの適合度、すなわち「戦略のフィット」、コスト・リーダーシップ、差別化、集中といった「基本戦略」、目標、戦略、戦術という「戦略のヒエラルキー」などを妄信するあまり、往々にして競争力の低下が招かれた。一方の新興グローバル企業は、戦略というものを、欧米流の経営思想とは根本的に異なる視点から考えている。
このような競争相手を前にしたのでは、これまで正統とされてきた手法を多少手直ししたくらいでは、オペレーション効率を心持ち引き上げるのと同じく、競争力の回復にはつながらないだろう(囲み「対照的な2つの戦略」を参照)。