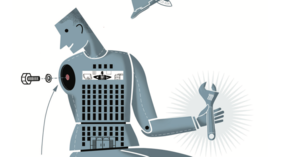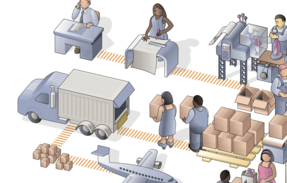-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
ウォルマート成功の秘密
1980年代、時間という資源が競争優位の新たな源泉であることが明らかになった。しかし90年代には、この時間という要素も、競争原理の変化の一つにすぎなかったと気づくことだろう。
いわゆるタイム・ベース競争で優位にある企業、つまり新製品を迅速に市場に投入し、ジャスト・イン・タイムで生産し、顧客のクレームに素早く対処できる企業は、往々にして、そのほかの面でも優れているものだ。
たとえば、高い品質水準を維持し続ける、あるいはますます高度化する顧客ニーズを正確に見抜くといったことが可能だろう。あるいは、新興市場を開拓したり、新規事業を立ち上げたり、新たなアイデアを開発したり、そこから新たなイノベーションを巻き起こしたりすることもできるだろう。
これらはすべて、その企業の基本特性を反映したものである。ひるがえって、これこそ、我々が「ケイパビリティ・ベース競争」と呼ぶ新たな企業戦略のコンセプトでもある。
ここで、ウォルマート・ストアーズとKマートの大逆転劇を紹介しながら、ケイパビリティ・ベース競争という新たな世界をのぞいてみたい。
79年当時、Kマートは、ディスカウント小売業界のリーダーとして君臨していた。これは、だれのおかげでもない、おのれの努力の賜物であった。Kマートは1891店舗を擁し、店舗当たり平均売上高が725万ドルで、規模の面で圧倒的に優勢に立っていた。そのおかげで、購買、物流、マーケティングなどで規模の経済を享受することができた。マネジメントの教科書を開いてみれば、まず例外なく、低成長の成熟業界で競争を勝ち抜くには規模の経済が不可欠と書かれている。
これと対照的に、時同じ頃、アメリカ南部の弱小小売りであったウォルマートは店舗数わずか229店で、店舗当たり平均売上高もKマートの約半分にすぎなかった。これでは、とても相手にならない。
ところが、それからわずか10年間で、ウォルマートは自社のみならず、ディスカウント小売業界の改革に成功する。年25%近い成長を遂げた同社は、単位面積当たり売上高、在庫回転率、営業利益に関して、ディスカウント小売業界の首位に立った。89年のウォルマートの売上高税引前利益率は8%で、Kマートのほぼ2倍に達していた。