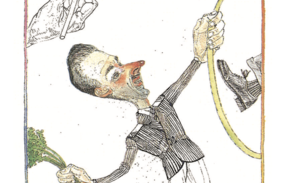-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
X理論とY理論
この30年間、マネジャーたちは、2つの対立する理論をさんざん聞かされてきた。それらは、人事と組織の問題に関するものである。
一つは、指揮命令系統をはっきりと決め、職務を明確に定義し、責任に見合った権限を与える必要性を訴えるもので、組織の古典学派と呼ばれている。もう一つは、社員のやる気が高まるように意思決定に参加させることが望ましいと主張するもので、参加型アプローチと呼ばれている。
ダグラス・マグレガーは、その有名な「X理論とY理論」で、モチベーションに関わる仮説を次のように区別した。この仮説は、先の2つのアプローチの基礎になるものだ(囲み「X理論からZ理論へ」を参照)。
・X理論によれば、人間は生来、仕事することが嫌いで、組織の目標達成に向かって強制的に従わせ、管理し、命令しなければならない。さらにほとんどの人間が、責任を回避できるため、この方法で処遇されるのを好む。
・Y理論は、個人の目標と組織の目標を一致させることを論じている。平均的な人間は本質的に自分の仕事に関心があり、自律を望み、またしかるべき責任を求める。そして業務上の問題を独創的な方法で解決する能力があるという。
マネジャーたちが従うべきは、当然ながら後者のアプローチであるというのが、マグレガーの結論である[注1]。
X理論からZ理論へ
X理論とY理論は、アメリカの社会心理学者であるダグラス・マグレガー(1906~1964年)により、その著書『企業の人間的側面』のなかで提唱されたものである。
X理論とY理論は、人の働き方に対する2つの見解を表しており、2つの対照的なマネジメント・スタイルをも意味している。
X理論は言わば「性悪説」であり、たいていの人間は怠け者で、働くことを嫌い、彼らから成果を引き出すにはアメとムチを使い分けなければならないという。たいていの人間が基本的に未熟で、しかるべき方向を示してやる必要があり、責任を負う能力がないと仮定している。
したがって、X理論によるマネジメント・スタイルでは、具体的に規定された仕事を与え、たえずしっかりと監督する必要があることになる。また、人々を動機づけるには、懲罰をもって脅すか、賃金を上げることを約束するというやり方になる。マグレガーによれば、部下の不信感や敵意を招きかねない独裁的なスタイルになる。
逆にY理論は性善説であり、人間には実は働きたいという心理的欲求があり、達成感と責任感を求める成熟した大人であるという前提に立っている。
この考え方によれば、マネジャーと従業員の間により協力的な関係をもたらす可能性がある。Y理論のマネジメント・スタイルは、個人の欲求や目標が企業目標につながり、調和するような労働環境を確立しようと努めるものになる。
『企業の人間的側面』においてマグレガーは、Y理論があらゆる問題の万能薬ではないと認めている。彼はこのような概念にスポットライトを当てることによって、人間の可能性を制限するX理論の考え方をマネジメントが放棄し、Y理論で示される手法を考慮に入れることを望んだのである。
「欲求5段階説」で知られるアブラハム・マズローは、マグレガーに私淑しており、X理論とY理論を強く支持していた[注1]。そこで、彼はY理論をカリフォルニアのエレクトロニクス工場で試してみた。ところが、これはうまくいかず、何らかの方向づけや仕組みが必要であることを発見した。マズローはこの後、X理論による安全確保と方向づけの要因を取り入れた改良版Y理論を提唱した。
またマグレガーは晩年、X理論とY理論には矛盾点があるという批判に応え、それを解決する一歩進んだ理論を開発し始め、この理論を「Z理論」と呼んだ。これは、人間は経済的安定を確保すると、金銭的報酬の重要性が低下し、称賛や尊敬を勝ち取ること、成功や自尊心が重視するようになるという考え方だが、これを確立する前に他界してしまう。
1970年代になり、日本的経営の研究がさかんになると、日本企業の従業員の生産性がなぜ高いのか、X理論でもY理論でも説明できないことから、ウィリアム・オオウチが81年、新生Z理論として『セオリーZ』[注2]を上梓し、日本的経営の特徴である「終身雇用」「コンセンサス重視」「集団責任制」など、労働者に高い生産性と動機づけをもたらすと説いた。
【注】
1)Abraham H. Maslow, Maslow on Management, Wiley, 1998.(邦訳『完全なる経営』日本経済新聞社、2001年)を参照されたい。
2)William G. Ouchi, Theory Z, Addison-Wesley, 1981.(邦訳『セオリーZ』CBSソニー出版、1981年)
[参考文献]
『世界を変えたビジネス思想家』ダイヤモンド社、2006年
このマグレガーの見解のせいで、相対立する2つのアプローチのどちらを選択すべきかに悩んでいるマネジャーたちは戸惑いを感じている。マグレガーがX理論と結びつけている古典的な組織マネジメントは、状況によっては有効だが、実際、マグレガー自身が指摘しているように、それがうまく機能しない時もある。同時にY理論に基づくアプローチも、ある状況では好ましい結果を生み出すが、常にそうであるとは限らない。
すなわち、どちらのアプローチも効果的な場合もあれば、そうではない場合もあるわけだ。これはなぜなのか。そしてマネジャー諸氏は、この悩ましい状況をどうすれば解決できるのだろうか。