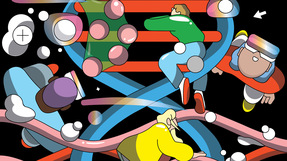-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
従業員不在のAI導入はありえない
AIは従業員を怯えさせている。従来は人間がするものだった知的要件の高い仕事を次第に機械がこなすようになるにつれて、従業員はこれまでになく、疎外されているとか、必要とされていないという感情を募らせている。しかもこの問題は悪化しつつある。
市場調査会社のバンソン・ボーンによると、ハイパーオートメーション──なるべく多くのビジネスプロセスを始まりから終わりまで自動化すること──を主要技術目標に挙げる組織は80%に上る。そして企業幹部には、この目標の達成によって仕事や生活に最も大きな影響を受ける人々、すなわち従業員からのフィードバックをまったく受け取ることなく、これを推進しようとする傾向がある。
しかし筆者が企業への新興技術の導入を数十年にわたって調査する中で、幾度となく証明されてきたことが一つある。それは、最も敏腕なリーダーは、導入プロセス全体で従業員の参加を優先するということだ。
このプロセスから従業員を疎外すると、彼らはAIとともに働くことを嫌がるようになり、AIの機能に対する信頼を育もうとせず、AIの活用がもたらす前向きな変化にさえ反発する。しかしながら適切に実行すれば、人間とAIのコラボレーションは最も有望な働き方となる。それは必ずしも最も速く、安く、容易なAIの導入・活用方法ではないかもしれないが、従業員を疎外するようなやり方は選択肢としてありえない。
このことを表す、ニューヨーク大学サイバーセキュリティセンターの研究者らの事例を見てみよう。研究チームは、ギットハブが開発したプログラム自動生成ツールのコパイロットを使用し、人間のプログラマーからの情報をまったく入力せずに、1692本のソフトウェアプログラムを作成した。すると、それらのプログラムの40%にセキュリティ上の致命的な欠陥があったという。
本稿では、リーダーがAIプロジェクトに従業員を参加させることを妨げる要因、リーダーが包括的な行動をモデル化する方法、そして従業員参加型のAI活用の取り組みを推進するために組織がすべきことを分析する。こうした取り組みによって、長期的に業績が改善し、従業員の幸福度、生産性、エンゲージメントが向上する可能性を高めることができる。