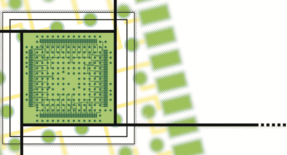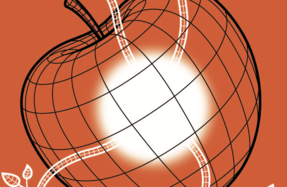-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
自社とライバルに続く第3の存在が軽視されている
いみじくも兵法の教えのように、ビジネスでも「おのれを知る」ことこそ最も重要な心得であり、これに続いて大切なのが「敵を知る」ことである。そして、近年の産業界において徐々に重要性を増しつつあるのが、「友を知る」という第3の心得である。たとえば、20年ほど前からSCMに注目が集まっていることは、この心得が重視されるようになった好例である。
自社の浮沈を左右するビジネス・パートナーは、何もサプライヤーや流通業者だけではない。相互依存関係にはないが、顧客を共有し、補完的な製品やサービスを提供する企業──以下、補完企業と呼ぶ──もまた、自社の命運を握っている。
自社製品とその補完製品は、互いに顧客価値を高め合う関係にあり、このおかげで両者が共有するパイは大きくなる。したがって、補完企業は、サプライヤーや流通業者に劣らず重要な存在である。
今日、補完企業として世界一有名なのは、おそらくインテルとマイクロソフトだろう。しかしこれは、数ある事例の一つにすぎない。印刷業界、写真業界、テレビ・ゲーム業界、自動車業界などにも、同様の例がある。補完企業は、自社の新製品の成否を左右するだけでなく、自社の命運にも影響を及ぼす。
たとえば、デジタル・カメラがここ数年で急速に普及したのは、安価な家庭用フォト・プリンターの開発、フラッシュ・メモリー、店頭プリント・サービスという要素が深く関係している。
自動車メーカーが将来、燃料電池車の普及という夢を実現させるには、水素スタンドの普及が欠かせない。同様に、電子機器メーカーは現在、電子書籍事業に取り組んでいるが、これを成功させるには、多種多様なコンテンツが安価に提供されなければならず、それには出版社の協力が不可欠である。
昨今、多くの企業が力を入れているのは、明らかに自社に優位性があり、しかも顧客ソリューションを完成させるにはサード・パーティの製品が必要な事業である。したがって補完企業と戦略的に提携することは、このうえなく重要な課題である。
ところが、ライバルやサプライヤーについて、巨費を投じて綿密に分析する企業は多いが、補完企業についても同様の分析を試みる企業は、驚くほど少ない。その原因は、経営陣にあるかもしれない。
経営上層部の人々は、補完関係について問われても、そのメリットのことしか考えず、利害の不一致による損失、戦略上の利害を一致させる必要性、それにかかるコストなどに思いをめぐらすことはない。SCMに優れた企業も、直接取引することのない相手と連携することがうまいとは限らない。
相互補完し合う企業同士は、市場の拡大という目標をはじめ、数多くの目標を共有している。しかし、両者の利害は対立することも多い。市場の拡大という共通目標ばかりが取り沙汰されるが、両者の事業の経済性や戦略は、そもそも根本的に異なっていることを忘れてはならない。