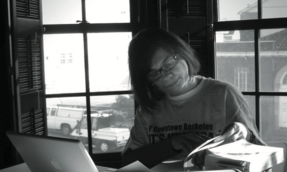-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
「弁証法」を知るために
「弁証法」という時、まず我々が思い浮かべるのはドイツの大哲学者、ゲオルク W. F. ヘーゲルだろう。大学時代にヘーゲルの著作を手に取った読者も多いだろうが、その難解さに途中で投げ出した方も少なからずおられるのではないだろうか。
本特集では、「マネジメントに弁証法的思考をどのように生かすのか」という視点だけでなく、哲学の立場から弁証法そのものに関する解説が必要と考えた。しかし、あの難解な弁証法を平易に解説できるものなのだろうか、はたしてその適任者はだれなのだろうか──。
さまざまな文献などの情報から、我々はジャック・デリダ[注1]の弟子であり、ヘーゲル哲学の研究者であるカトリーヌ・マラブー博士を知り、幸いにも今回弁証法についての質問に答えていただくことができた。
マラブー博士はデリダの脱構築とヘーゲルの弁証法、マルティン・ハイデガーの存在論の生産的な問い直しを続け、現在フランスで最も注目される哲学者の一人である。彼女は「可塑性(プラスティシテ)」をキーワードにヘーゲル哲学を建設的に読み解き、その思考をニューロ・サイエンスやグローバル化にまで展開する。さらには日本文化についても造詣が深い。
このように、マラブー博士はさまざまな知を持っており、それを巧みに操りながら、弁証法についてきわめて魅力的に語ってくれた。
弁証法の思考法
DHBR(以下色文字):いま日本の産業界では、「論理的に思考する」ことの重要性があらためて指摘されています。
しかしその一方で、より創造的な発想には、このような線形思考を超えた思考法が必要であると主張する人たちが少なくなく、その一つが「弁証法」であると指摘しています。
はたして弁証法は、豊かな知識を創造したり、新たな知見を導き出したりするうえで有効な方法といえるのでしょうか。ヘーゲルの言うところの弁証法について、日常的な例を用いてご解説いただいたうえで、あなた自身、どのように弁証法的に思考しているのか、同じく例をご紹介ください。
マラブー(以下略):ご質問にお答えする前に、申し上げておきたいことがあります。それは、「日本はきわめて弁証法的な国である」ということです。その理由については、後段にご説明したいと思います。
哲学という世界は、いつの間にか、その分野の専門家同士が抽象的で奇妙な隠語を使い合うようになってしまいました。