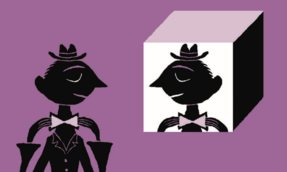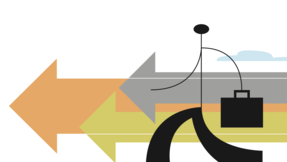-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
なぜ後継者の多くが期待に応えられないのか
企業の長期的な活力源として、リーダー層の選抜と育成ほど重要なことがあるだろうか。ところが現実には、事業部長が務まるはずの、綿密な候補者リストを作成しているにもかかわらず、いざその地位に就けてみると、準備不足で派手に失敗するケースはごまんとある。
コカ・コーラで長らくCFOとしてロバート・ゴイズエタの右腕を務めたM. ダグラス・アイベスターが典型例だ。ゴイズエタの死後、アイベスターはCEOの座を引き継いだものの、株価の大幅下落、PR活動の失敗、ヨーロッパで起きた汚染問題の対応ミスなどが重なり、わずか2年半で辞任を余儀なくされた。また玩具大手のマテルでは、ジル・バラッドがマーケティング畑での華々しい実績を買われてトップに就任したが、大企業の財務面、戦略面の洞察に欠けていた。
これらの敗因は、経営の少なくともどこか一面については明るくても、たとえばPR、買収計画の立案・実行、コンセンサスの形成、さまざまな関係者との折衝など、企業経営に欠かせない全般的な能力が身についていなかったためである。
前任者の抜けた穴が大きすぎるという指摘もあるが、それだけではない。一般に考えられているサクセッション・プラン(後継者育成計画)はあまりに限られた人々の手に委ねられているため、経営者としての仕事とスキルのギャップを前もって解消できないでいる。これでは、有望な若手エグゼクティブがつまずくのも無理はない。
我々がリーダー層の成功と失敗について調査したところ、候補者リストを機械的に更新することなく、より丹念に手間をかけて、「控え選手」の層を厚くしている企業の存在を発見した[注]。
こうした企業は、2つの仕事(サクセッション・プランとリーダー層の育成)を一つにまとめ、全社から人材を登用する長期的なプロセスを確立している。凡百の企業では、サクセッション・プランとリーダー層の育成を担当する部署は分かれているが、本来は並行して考えるべきものである。適材を適所に配する、という基本的な目的はまったく同じなのだから。
イーライリリー、バンクオブアメリカ(バンカメ)、ダウ・ケミカルなど、洞察力に富んだ模範企業は担当部門の壁を取り払い、サクセッション・マネジメントと呼ぶべきプロセスをまとめ上げている。以下、各社の実例を交えつつ、トップにふさわしい人材を安定供給するパイプライン、すなわちサクセッション・マネジメント・システムの5つの原則を説明しよう。
[原則1]
育成に力を惜しまない
第1の原則は、5原則すべての基礎となる。サクセッション・マネジメントは、単に能力の高い社員とそのためのポストを抽出するだけでなく、育成活動を中心とした柔軟なシステムでなければならない。トップ層のサクセッション・プランとリーダー層の育成を結合させれば、双方がフルに力を発揮する。社員たちもおのずとさらに上のスキルを目指し、また教育システムも洗練されていく。