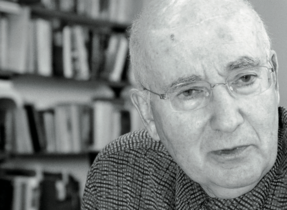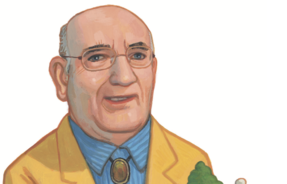-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
品種過剰との悪戦苦闘
ほとんどの企業が、多種多様な製品を扱っている。規模の大小にかかわらず、またメーカー、卸売業、小売業など、業種が異なろうとも、多岐にわたって大量の製品を扱っている。
たとえば、標準的なスーパー・マーケットは6800品目を取り扱い、アメリカン・オプティカルが製造している品目は3万種余り、またゼネラル・エレクトリックの製品と部品の種類は数十万に達する。
そもそも製品ラインの規模は、製品の取捨選択という、体系的かつ定期的な経営努力がなければ、長年の間には膨れ上がっていく。概して経営陣は、既存製品の撤退よりも、新製品の追加のほうがたやすいと考えがちである。しかし実際には、製品や製品ラインの数が増加するにつれて、経営陣が考えるべき問題の範囲は幾何数的に拡大していく。
経営陣には、品種過剰、それゆえ製品すべてには手が回らなくなるという、マルサス的な不安[注1]がしのび寄る。限られた経営資源の配分は、金融面でもマーケティング面でも、大量かつ多品種の製品にあっては、広く薄くという具合にならざるをえない。
その結果、この問題は次の2つの大きな問題へと発展していく。
(1)売上げ予測と価格設定において、自社製品の間で増加しつつある「相互需要」の関連性に対処しなければならない。
(2)生産計画、原価計算、設備投資において、自社製品間に増加しつつある「相互供給」の関連性に対処しなければならない。
品種過剰はまた、経営資源の配分と調整においてやっかいな問題をもたらす。その対応策として、経営陣はいままで以上に生産ラインのスリム化に専念することが肝要である。競争が激化し、数多の製品に消費者が食傷するにつれ、戦力外の製品ラインを取捨選択する必要性が、代替製品の開発と同様に増大する。
取捨選択の必要性は、多くの企業で次第に認識されるようになってきた。次のような卑近な例がある。
・アメリカン・モーターズのケルビネーター事業部[注2]が、冷蔵庫やエアコン、キッチン用品の製品ラインにおけるモデル数を大幅に縮小させた。