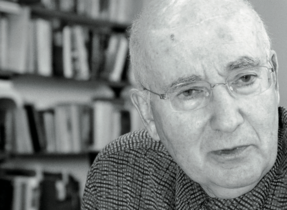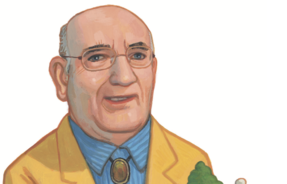-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
マーケティングを科学的に意思決定する
産業界では、在庫管理、生産計画、物流センターの立地選定、配送ルートの決定、財務計画など、多くの分野で意思決定の定型化が進み、快く受け入れられてきた。これら分野の諸問題解決に高度な数的処理、すなわちオペレーションズ・リサーチ(以下OR)の発想を取り入れることは、もはや珍しくはない。それどころか常識となっているようだ。
ところが、ことマーケティングに限っては事情が異なる。アメリカでは、マーケティングの意思決定の99%以上がいまだに直感に従って下されており、高等数学とは無縁のようである。
多くの人々がこれを当然と考えているようだ。マーケティングにまつわる意思決定は、他の分野とは違って一筋縄ではいかない場合が多い。というのも、正確な情報などけっして得られはしないからだ。競争は激しく、顧客の行動は予想がつかない。しかも、マーケティングの効果は時間が経たなければ見えてこないばかりか、さまざまな条件に左右される。このような状況でORなど役に立つはずがない。
しかし現実には、ORはマーケティング分野でも成果を上げつつある。実際、これまでの単純なマーケティングを捨てて、より洗練された手法を用いてマーケティング上の意思決定を下そうと、毅然とした態度で取り組んでいる企業が少ないながらも現れている。そのような企業は、マーケティングは複雑だからこそ、理論や分析を積極的に取り入れるべきだと考えている。
このような動きを知らない人たちは、まず現状を見つめ直すべきだろう。逆にすでに承知している人たちは、どのような成果が上がっているのか、詳しく探ってみるとよい。本稿は、これら2つの広範な視点をカバーすると共に、以下の4つの具体的問題に答えることを目的としている。
(1)定量的マーケティングのきっかけとは何か。
(2)具体的にはどのような事例があるのか。
(3)今後の発展として、そのような兆しが表れているのか。
(4)定量的マーケティングから、どのような成果が期待できるか。組織上のハードルがあるとすれば、それは何か。
乱数を用いたシミュレーションを何度も行うことにより近似解を求める計算手法。第2次大戦中のアメリカで、コンピュータの父と呼ばれるジョン・フォン・ノイマンらが、中性子が物質のなかを動き回る様子を探るために考案した手法が起源とされる。この分析手法は、マーケティング・リサーチをはじめ、金融工学など、経営のさまざまな分野に応用されている。
第2次世界大戦後、1947年にアメリカの数学者G. B. ダンツィグによって開発された。与えられた条件の下、相互に関連している変数において最適な解を得るためのプログラムである。産業界においても、利潤の最大化や費用の最小化などのための最適化手法として幅広く利用されている。
クリティカル・パスとは、ある作業が少しでも遅れる場合、全体のスケジュールまでも遅れてしまう地点のこと。この地点を明らかにし、何らかの活動やプロジェクトにおいて、多くの作業内容を調整し、複雑な製造プロセスを一つの最善のスケジュールに組み立てること。
投資の費用対効果を最大化するためのシミュレーション。
市場テストの結果を分析し、顧客における知名度、購買動機、選好、購買行動などについてシミュレーションし、マーケティング・ミックスを改善させる。
18世紀のイギリス数学者、トーマス・ベイズの提唱した確率論。何かが起こる可能性はその事柄の過去の発生頻度を使ってほぼ推測ができるというもの。
ある問題について必ずしも正解が導けるとは限らないが、経験則に基づいて、なるべく正解に近い解を得るような解法のこと。
マサチューセッツ工科大学のJ. W. フォレスター教授によって提唱されたもので、受注から納品に至るまでに必要とされる経営資源と情報の流れを分析し、モデル化し、これらをシミュレ-ションすることで、環境変化に適応するための施策を見出すことを目的としている。詳しくは『インダストリアル・ダイナミックス』(紀伊国屋書店、1971年)を参照。
ハイ・アセイとは、金属高含有量分析という意味で、それぞれ異なった含有量を持つ金山に対して、資金をどのように割り当てるかという問題から来ている。このモデルに、消費者の商品反応、媒体反応、広告反応のデータを入力することで、到達見込客当たり最低費用の媒体を抽出する。
ブランドの選択など、さまざまな消費者行動を定量的に分析する手法。モデルの仮定によれば、消費者は製品に満足すれば満足の「はしご」を上ってより満足度の高い状態へ移るが、反対の場合には「はしご」を降り、最後には他のブランドへと推移してしまう。他ブランドへの移行はブランド魅力度で決まり、各プロセスは確率的に行われる。
マーケティングとORの融合
第2次世界大戦の直後、在庫管理と生産の両分野でORの画期的なイノベーションが成し遂げられ、以後ORは20年以上にわたって発展を続けてきた。にもかかわらず、マーケティングとORの融合は未熟な段階にとどまっている。